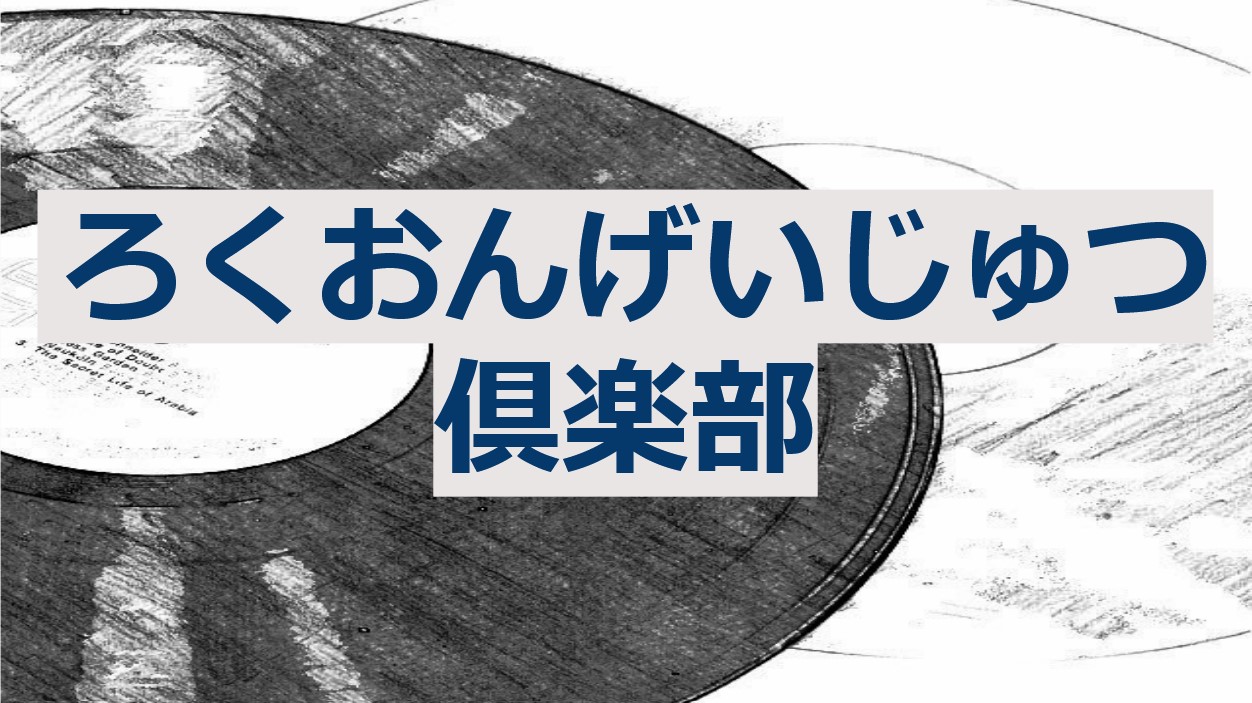ライブは休日のお昼のイベントで、対バン形式で僕らの他に五バンドが参加することになっていた。持ち時間は一バンド三十分位。MC含めて大体五、六曲できる計算だ。ということで今形になっている曲は十曲だからそれをスタジオで煮詰めて、最終的に、六曲に絞り込むことにした。
その時の僕は頭ごなしに無理だと否定したがバンドなんて二人もいれば十分いいライブが可能である。フォークミュージシャン達はアコースティックギター(と時々ハーモニカ)と歌だけで、多くの聴衆を魅了してきたし、ビリー・ブラッグは最初、歪ませたエレキギターと歌だけのアルバムを作っていた。ジェフ・バックリーの代表曲は魂を揺さぶる彼の歌とテレキャスター美しい音色だけの「ハレルヤ」だし、ホワイト・ストライプスはギターとドラムだけで何万人も入るフェスの会場を湧かせていた。バンドだからといって、ギター、ベース、ドラムがそろってないと感動的なライブができない、というわけでは全くない。ただ「みんながそうしているから」という理由で僕はベースとドラムがいなければ何にもできないと思い込んでいた。一方、高岸は「今なにをすることがベストなのか」常に考えていた。
というわけで残り一ヶ月弱、僕達は可能な限り集まって曲を練り、週二回ぐらいのペースで二人でスタジオにも入った。高岸が作った曲がメインだったから彼が基本ギターを弾きながら歌うので、何曲かは僕がドラム叩いたりすることになった。しかしどうしてもギターが二本要りそうな曲や、僕の拙いドラミングでは心許ない曲では高岸の持ってるドラムマシーンを使った。僕たちはその黒くてでかいドラムマシーンを※①エコーと呼んだり、ビッグ・ブラックと呼んだりしていた。高岸は僕が用意してきた、例の曲になりきってない断片的なフレーズをなんとか曲の形にアレンジしてくれたので、※②その曲も一曲やることになり、それは僕が歌うことになった。
ということで最終的に六曲が用意され、
1.高岸ギターボーカル、僕ギターとコーラス、ドラムマシーン
2.僕ギターボーカル、高岸ギターとコーラス、ドラムマシーン
3.高岸ギターボーカル、僕ドラム
4.二人でギターボーカル
5.高岸ギターボーカル、僕ドラム
6.高岸ギターボーカル、僕ギターとコーラス、ドラムマシーン
のセットリストになった。
本番当日は僕が自分の機材、ギターやエフェクターを持って高岸のうちに行き、彼の機材の一部を持って、高岸は自分のギターとドラムマシンを持っていった。僕たちの出番は最初から二番目という、一番どうでもいいポジションだったが、それぐらいがむしろ僕らには好都合だった。ライブ本番前に軽くリハーサルがあって、出番の遅い順にトリからリハーサルをするので、二番目の僕らは割と遅めの到着でよかった。
たまにリハーサルを最後の練習と勘違いしているようなバンドがいるがリハーサルは出音のバランスや(演者がステージ上で聴くモニターからの)音の返しをチェックするもので、基本的に一曲毎にワンコーラス確認して終わりである。僕たちは変な編成で曲によって音量バランスが変わるので、結構時間がかかってしまった。僕らは地元でそれぞれ二回程度しかライブをやった経験しかなく、若干不慣れということもあった。
会場には僕らの知り合いが若干名きてくれたが、それはチケットをあげたうちの十分の一ぐらいの人数だった。一組目は※③ハイスタに影響を受けたようなメロコアバンドで、技術はあったけど歌詞がいまいちで僕らは自分を棚に上げて苦笑していた。それでも結構人気があるらしくて(まぁ全員友達とかなのかもしれないけど)それなりに盛り上がっていたし、ステージ前は賑わっていた。僕たちは彼等の演奏が二曲終わると、準備のために舞台袖に消えた。
バンドの経験なんて社会では役に立たないと思うかもしれないが、僕はそんなことは無いと思っている。チームの運営に必要な能力が身につくし、多くの人の前でプレゼンするような度胸が付いたのは間違いなく、ライブでの経験があるからだ。そしてライブで堂々と演奏出来るか否かはどれだけ練習してきたか、数こなしてきたか、事前に準備してきたかによる。それはプレゼンテーションの場においても同様だ。
話を戻そう。出番がきた。僕たちはガチガチに緊張していた。正直僕がステージで思うようにプレイ出来る様になったのはW3を始めてからで、それまではこの緊張をうまく乗りこなせず、大して無い実力の更に何割しか発揮できていなかった。そしてその時は高岸の方が僕よりも緊張していた。先程はあんなにステージ前は混雑していたのに、僕らの出番になるとそこにはポッカリとスペースがあって、僕らの知り合いが遠慮がちにステージ端っこの前の方にいた。
「どうも、Katie’s been goneです」と若干声を震わせながら高岸が言うと僕はドラムマシンをスタートさせた。
※④一曲目は高岸がギターボーカルで僕がギターとコーラスを担当するパワーポップチューンで、ドラムマシーンのパターンがやや単調だったが、当時僕らが二番目に自信があった曲で、一曲目が終わる頃には僕たちの緊張も大分ほぐれてきていた。二曲目は例の僕が素材を持ってきて高岸が完成に漕ぎつけてくれた曲で、僕がギターボーカル、高岸がギターとコーラスを担当した。高岸は一曲目が終わった後に軽く喋ってドラムマシーンをスタートさせた。僕の曲はそもそもギターフレーズから無理やり曲に仕立て上げたこともあって歌自体の力に乏しいのでアレンジで聴かせるしか無い。よってドラムのプログラミングもギターフレーズも結構凝った物になった。とっつきにくい事もあり反応はいまいちだった。三曲目は高岸がギターボーカルで僕がドラムを叩いた。6/8拍子のスローなフォークロックナンバーで元の楽曲の力で聴かせるタイプの曲でアレンジは簡単だった。次は二人で歌いながらギターを弾く、ザ・バーズを下敷きにしたフォークロック的なアレンジの曲をやり、五曲目は高岸ギターボーカル、僕がドラムでザ・バーズの「すっきりしたぜ」(I’ll Feel a Whole Lot Better)をやった。最後はストーン・ローゼズの「Waterfall」みたいな四つうちのドラムが気持ちいい高岸の自信作だった。ドラムマシーンに合わせて僕はギターリフを繰り返し、高岸は基本的にボーカルに専念して、サビで僕は彼の歌にコーラスをつけ、最後に高岸がギターソロを弾くという構成で、これに関しては観客が前のめりになって聴いてくれてるのがわかって気持ちが良かった。高岸のギターソロもスタジオで前もって作ったフレーズと全然違うものだったけど、むしろ本番の方ができが良かった。唯一残念だったのがギターソロが長くなってしまったため、ドラムマシーンが先に演奏を終えてしまい、終わり方がなんだかしまらなくなってしまった事だったが、それだって高岸がギターをフィードバックさせてなんだかそれっぽくまとめて締めたのであった。僕らは知り合いによるまばらな歓声を浴びてステージを降りた。初めてにしては成功と言ってもいいと思う。
終わった瞬間に僕らは顔を見合わせた。「結構良かったよな」「うん、良かった。特に最後な」「けどギターソロ長すぎたな」というようなことを僕らは表情で語った。客席の暖かな歓声が嬉しかった。
素人バンドの退場はいつも不細工である。ローディーがいるわけでもないのでいそいそと自分たちで機材を片付けるしかない。格好良く退場してそれで終わりとはいかないのだ。終業式後の小学生の下校みたいに荷物を沢山抱えて僕らは控え室にはけた。
興奮しつつも黙々と控え室で自分達の機材を片付け、やっとステージの方に戻ったら三組目のバンドはもうほとんど終わりかけていた。スカとパンクを融合させたような伴奏に、本当は※⑤ジュディマリみたいなのがやりたいんだろう、YUKIに大分歌唱スタイルを寄せてた女性ボーカルのバンドだった。
四組目は本当に全然覚えていない。五組目も全く覚えていないけどおじさんバンドで観に来ていた人に子持ちが多かったのは覚えている。
そしてトリで出てきたのが※⑥Etherwiseという、四人組のバンドだった。エーテルワイズはギター(男)とベース(女)のツインボーカルのバンドで、彼らの掛け合いとコーラスワークが大きなウリの一つだった。僕たちは出番の前後のバンドはちゃんと観れてないが、一応四バンド目以降はきちんと観ていた。そして今回出演した全てのバンド(勿論僕らを含む)の中で一番良かったのがエーテルワイズだった。中でもベースの女の子が歌う曲がポップだけどエッジがかなり聴いていて、ある意味僕らが目指していたXTCやコステロみたいな攻撃性を有したパワーポップ、という方向性に近かった。対してギターの男のほうの歌はまぁ悪くはなかったがベースのボーカルに比べると曲のインパクトに欠けた。そうしてライブイベントは盛況のうちに幕を閉じた。
イベントの主催バンドでもあったので、エーテルワイズを中心に、この後ライブの打ち上げが居酒屋であるようだった。僕は正直かなり疲れていたのと、他のバンドの音楽性にさして興味がもてなかったのもあり、早く帰りたかったが、高岸はなぜか行く気満々だった。
「帰ろうぜ、ただでさえ金欠なんだからさ。第一俺らが打ち上げいって楽しめるわけないじゃん」高岸はそれを無視して「あの最後のバンドのベースボーカル、よかったよな」と言った。「確かに良かったな。演奏も上手かったし、歌もフックがあった」「あの人、うちのバンドに誘おうと思ってさ」
高岸の行動力には何時も驚かされるがこれは全く予想できてなかった。問題の彼女はなんだかよくわからない取り巻きに囲まれていて近づくのも大変そうだった。それだけで僕はもう面倒くさかった。僕らが相手にしてもらえると思ってなかったし、ライブ前は散々ベースとドラムの必要性を高岸に説いてきたにも関わらず、今日のライブに手応えを感じた僕は、バンドを「二人だけで」育てていこうと勝手に決意したばかりで、第三者の力なんて求めていなかった。高岸が何かを言い出したら頑として動かないのはもう散々わかっていた。そしてなによりも高岸が正しいのも分かっていた。単純な足し算でいえば、彼女が万一参加してくれるならバンドにとってプラスになる事は間違いなかった。だから僕も強く反対せずに「無理だと思うけどな」とかぶつくさ言って機材を担ぎながら会場へついて行った。高岸は「無理だったらさっさと帰ればいいじゃん」的な微笑を浮かべながら僕の少し前を歩いていた。
相変わらず飲み会で僕は不細工な立ち振る舞いだった。僕らは三組目のバンドと同席で、僕は飲み食いに集中して「うんうん」と近くの会話に耳を傾けているだけだった。高岸は大学サークルの新歓の時よりは進化していて会話になんとか混じることができていた。例のベースボーカルの周りには相変わらず人だかりが出来ていた。当時は明るめカラーのロングヘアで巻き髪の流行が始まる頃だったみたいだが、僕の周辺ではまだボブが流行っていたし、みんな髪を大なり小なり明るくしていた。そんなわけで※⑦黒髪ストレートロングの彼女は珍しかったのだが、それが彼女にはしっくりと来ていた。といってもそれは後でわかることでライブの時はそれを後ろでまとめて、所謂お団子ヘアにしていたと思う。まあそれは結構どうでもいいことで、今なんとなく思い出しただけだ。彼女が印象的だったのはその目だった。※⑧彼女の目はぱっちりしていて大きめで、なんとなく吸い込まれるような魅力があった。そしてその瞳の奥に、微かな情熱や意志を宿しているのが飲み会の席の遠くからでもわかった。そんなかたちで僕が彼女の方をぼんやりと見つめていると彼女と目があったので僕は慌てて目を逸らして目の前の唐揚げをつつきはじめた。このまま待っていても彼女の周りから人の波が消えそうにないので僕らは他の人達がやっているように他のバンドに挨拶回りすることで徐々に接近していく事にした。※⑨というわけで実に回りくどいやり方で三十分ぐらいかけて僕らは彼女の席までたどり着いた。たどり着いてから気付いたが、エーテルワイズの他のメンバーがいる中で彼女一人をバンドに誘うのは度胸がいる、というかおそらくマナー違反である。しかし高岸の中ではストーリーが組み上がっていたのだと思う。まずは彼らがどんな状況下で活動を行なっているのかメンバーに尋ねていた。
エーテルワイズは同じ大学のメンバーで結成された四人組で三年生と二年生から成るバンドだった。つまりはみんな年上だったのだ。例のベースの女性は石田さんで、彼女は二年生だった。ドラムは物静かなガタイのいい短髪の男で彼も二年。二人のギタリストは三年生だった。エーテルワイズの楽曲を作っているのは主に石田さんだった。僕は酷い偏見を持っていたんだと思う。彼女はバンドのマスコット的な存在で、与えられたものを歌っていると僕は勝手に思っていた。恥ずかしくなったと同時に僕の持っていない物をたくさん持っている石田さんが眩しすぎて僕は消え入りそうになった。
「最初はオレが作ってたんだけどさ、ケイちゃん(石田さんのこと)が作ってくる曲の方が全然いいから、途中から殆ど作ってもらうようになっちゃってさ」とギターボーカルはタバコを深く吸いながらなぜか自慢げに言った。ただ歌詞はもう一人のギタリストが主に書いているそうだ。という事で石田さんは我々が理想としていたようなパワーポップ的なソングライティングの術を取得している存在だった。高岸の見立ては間違っていなかった。そして我々にとってラッキーなのはエーテルワイズはどんなに遅くてもその年の秋口には解散が決まっているバンドという事だった。というのも三年の二人は秋から就職活動が始まるからという事だった。「就職活動」。その四文字で僕らは重い気持ちになった。当時は史上二番目の就職氷河期が開け始めた時期で、僕らは入学時から就活の準備を、一年からしておくに越したことはないというアドバイスを学生課からしつこく受けていた。僕たちは可能な限りその四文字を頭から追い出して生活していた。ひょっとしたら高岸はそうではなかったのかもしれないが。そんなわけでギタリスト二人は就職活動に対する愚痴や不満で盛り上がり始めたので高岸は早速石田さんに切り込んでいった。「よかったら僕らとバンドやりませんか?」僕だったから言うのに最低ひと月はかかりそうな言葉を高岸はチャンスを逃さずにあっさりと言ってしまった。これには僕だけでなく、例のドラムの彼も驚いていた。
「それって君たちのバンドに入るって事?」「まあ、そう言う事ですかね…」と高岸は言った。
沈黙が流れた。
実際には二、三秒だったかもしれない。永遠とは言わないけど一週間ぐらいには感じられた間だった。
「いいけど二つ条件があって、君たちドラムいないんだよね」「はい!そうです」高岸は必要以上に元気に答えた。「それならこの石崎くんをドラマーにすること。それから、私の名前、ケイって言うんだよね。だからケイティーズ・ビーン・ゴーンってバンド名はちょっと嫌かなって」
僕は苦い顔をしていたに違いない、けど隣を見ると高岸は承諾してくれた事に喜んでいたようで目がキラキラしていた。そうして、Katie’s been goneはその役目を終え、StraySheepsの物語が始まった。
※①エコーは、エコー・アンド・ザ・バニーメンが初期に使っていたドラムマシンに彼らがつけた名前でそこからとった。ビッグ・ブラックはドラムマシンと金属的でノイジーなギターサウンドで知られる80年代のバンド。ニルヴァーナのプロデュース等で知られるスティーブ・アルビニがやっていたバンドだ。
※②「The Headache Production」という曲。歌詞を一部載せようと思ったけど恥ずかしいのでやっぱやめた。自らのアイデンティティを問う歌詞である。
※③柳のやっていたバンドではない。念のため。当時は本当にメロコアバンドが多かった。
※④ここから僕たちがライブでやった曲の解説が始まるが、皆さんが想像しているものをかなり酷くしたもの、と思って差し支えない。
※⑤ジュディマリ。1992年結成、2001年に解散した日本のロックバンドJUDY AND MARY (JAMともいわれていた)の略称。ボーカルのYUKIの女子からの支持はすごく、当時はすでに解散していたにも関わらず、ジュディマリのコピバンでボーカルをやりたがる人が多かった。が、バックの演奏が結構テクニカルで女子に「お願い、一緒にジュディマリのコピー、しよ」って頼まれて気軽に引き受けると痛い目にあう。
※⑥エーテルワイズは岩井俊二の『リリィシュシュのすべて』に出てくるエーテルという言葉と『サウンド・オブ・ミュージック』の挿入歌「エーデルワイス」との掛け合わせである。
※⑦僕だってこんなテンプレみたいな人物描写は嫌だ。けど事実だ。「黒髪ストレートロングなんて男の幻想なんだよ」とショートボブの錦は言ったから「じゃあ石田さんは?」といったら「あの人は色々例外なのわかるでしょ」。その通りだ。すまん。
※⑧そんなわけで僕は石田さんを思い出す時にシュメール人の事も思い出す。無論彼らの彫刻ほど目が大きいわけではないのだが。
※⑨というわけで5組めのおじさんバンドに最初に僕たちは話しかけた。完全に彼らを利用する形になり、多少なりとも良心が痛んだが、延々と会社の愚痴を聞かせられたので、まぁおあいこだ。