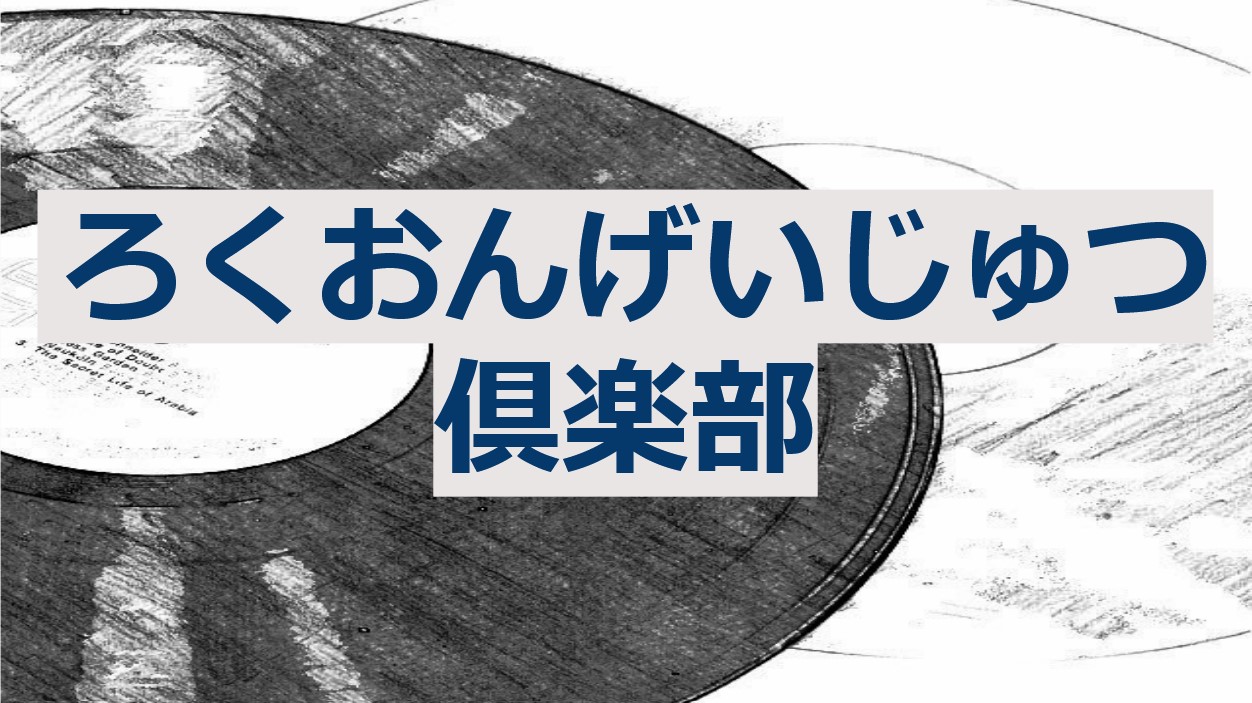StraySheepsとは対照的に我々W3は勢いづいた。StraySheepsとの対バンが決まったあと直ぐに、西沢君と僕は次のライブをすでに三件ぐらい入れていて、四人体制での初ライブの時、予定していたライブの告知をし、それらに関するフライヤーも作成済みで会場で配ったこともあり、集客は上々だった。成功したから良かったが、これは賭けに近かった。合計十万くらいはあったチケットノルマを西沢君と僕とで負担していた。これらのライブについては勿論柳と南さんには教えていたわけだが、やることはほぼ我々二人の独断で、ノルマもその二人からは徴収せず、二人でとりあえず五万くらいずつ肩代わりした。StraySheepsとの対バンの時点で次回のライブのチケット、持って来ていた分十枚は完売し、のこりのノルマ分も当日までに人づてに売れた。その次のライブのチケットも二回目のライブの時に売れた。二回目のライブでは僕のボーカルと曲を中心にやって、柳の曲と西沢君の曲は一曲ずつだった。三回目は西沢君の曲中心でやった。そのあとは一旦少し間をあけて、十月の中頃にライブを入れた。次のライブはどのような形式でやるか、三回目が終わった時点でなにも考えていなかったが、次のスタジオ入りの時決められばいいと思い、ぼんやりと柳、僕、西沢君それぞれのボーカル曲が大体均等になるぐらいのライブをすればいいかと考えていた。
「ぜんぜんだめっすね。それでは」
三回目のライブが終わって柳と南さんが帰った後、二人でファミレスに入り、次のライブについてどうするか思ってる事を話したら西沢君が言った。
「当面の目標ってライブでいまのメンバーでのベストを見せることじゃないですか。ていうか俺は勝手にそう思ってるんですけど、今の形態だと今のこのメンバーの実力を全然活かせてない気がするんです。思うに、今、俺たちってコンセプトをフォローすることにこだわり過ぎてる気がするんですよ。つまり複数ボーカルでやるってことに。ビートルズを理想に掲げてそうありたいっていってましたけど、ビートルズって、ドゥーワップとかの影響もあるのか初期はコーラスグループみたいなところがあって、そもそも全員で歌うというスタイルが出発点だったりするじゃないですか。だから誰がリードとっても不自然じゃない。でも我々の曲って全員で歌う様なものじゃないですし、日本の複数ボーカルのバンド、例えばユニコーンとかも最初は奥田民生のボーカルだけが前面に出てたし、YMOとかだって最初基本インストで、ボーカルがあってもボコーダーがかかってて誰が歌ってるのか気にならないぐらい匿名性が強くなってるんですよ。みんなある程度人気や認知が出てきたキャリアの中後期からなんですよ。複数ボーカルを打ち出してるのは。なぜならやっぱりボーカルが複数いると焦点がぼやけるというか、見てる側からするとどういうバンドなのかわかりにくいかなって思うんですよね」
それからじゃあ仮にボーカルを一人に絞るとしたら誰かという話になり、そこは二人とも柳だろうという事で一致した。歌がうまいとかそういうことではなく、「雰囲気がある」という理由だった。それに彼には独特の節回しがあって、なんというか癖になるずれがあることを二人で再確認した。けれども僕はまだまだ複数ボーカルでの活動に拘った。
「だからってわざわざできるものを絞らなくてもいい気がするけどな。いまから見てる側からのバンド像がぼやけない適切なバランスを考えていけばいいし、ボーカルが複数いるバンドっていう認識を広めてけばいいって話じゃないの。勿論理想は何度も言ってるみたいにビートルズで、ジョンとポールみたいにそれぞれ拮抗してる所にジョージがたまにスゲー曲を入れてくるみたいなバランスだけど、それをそのまま俺たちが取り入れた所でいいバンドになるとは僕も思ってないし。適切な見つかるまでは試行錯誤したらいいんじゃない?」
「だからもうそれが違うんと思うんですよ。複数のソングライターがいて、それぞれが作った曲を歌うことができるし、それは勿論強みだし、強烈な個性だとは思うんですけど、それぞれ違うベクトルに向いちゃってることには変わらなくて、完全にイメージですけど力が分散されてる気がして、それが自分らのベストじゃない気がするんです」
「じゃあなにがベストなんだよ」
「正確にいうと複数ボーカルなんて後でいくらでもやればいいんですよ。我々のイメージが固まったあとや行けるところまで行ったあとでいくらでも。ただ今は、今までのW3のイメージを殺さずに、延長線上にあるもっと凄いものの可能性を探ってみたほうがいいかなと思うんです。力を一点集中させて突破するみたいなイメージで。それを目指すには柳さんのボーカル中心になるのかなって思うんです」「ちょっと待て。柳ボーカルはいいとして、延長線上にあるもっと凄いものって、そんな夢みたいな話にどう向かっていったらいいんだ?」
「やってみないとわからないですけど、一つ方法があります」「なんだよ」
「共作です」
前に作曲の話になった時に僕は歌詞があれば曲は結構かける、しかし歌詞はなかなか思いつかない、という話をした。そしたら西沢君は「じゃあ柳さんの歌詞に曲をつければいいんじゃないすか」といった。柳は作曲する時、詩から先に書く珍しいタイプだったから、それが前提にあった発言だと思うが、それまでそんな発想は僕には無かった※①。彼は勿論柳に一目置いていたが、僕みたいに柳の信奉者ではなかった。だからそんな発想が出てきた。その時は流してしまったが、この話を今一度彼は議題にだしてきた。
「柳さんの曲。歌詞は凄いとおもってるんですけど。なにか足りない気がします。それはメロディーじゃないかと思ってて。メロディーに対するこだわりが比較的薄いじゃないですか。柳さんは。対して先輩のつくる曲はもっとメロディアスなので、補完しあえばもっと凄いのができるはずです。今はそれぞれのソングライティング能力が一曲一曲分散されてて、アレンジにしかそれが生きてない状態ですけど、それを一曲に集中させてみたらいいんじゃないかと思って。ビートルズも最初の方は共作でしたし、YMOも曲によってメンバーの組み合わせが違う共作曲が大半を占めてるじゃないですか。僕と先輩で作っても面白いモノができそうですけど、先輩と柳さん組み合わせの方が可能性を感じるんで、まずは柳さんと二人でやってみてほしいです」
西沢君のアイデアにとりあえず乗っかってみることにした。行き詰まりを感じてはいなかったし、今の方向性で間違いは特にはないと思っていたが、何か新しい試みをしてみるのも悪くないと思った。それで遠くまで行けるなら当時の僕ならなんでもしたと思う。試しに柳に歌詞だけで曲を付けてないものはあるかと聞いたらいくつかあるらしかったので、それに曲をつけてみてもいいかと聞いたらよいというので、歌詞の写しを何枚かもらって家に持ち帰って試しに曲をつけた。やってみて分かったのは、メロディをつける段階で結構な頻度で歌詞の細部を調整したくなるということだった。出来上がったものをまず柳に聴かせる前に歌詞で変えていい部分とそうでないものを、これならいい、ここはだめ、代わりにこのいいかえならOK? などと確認して少し変えた。そうして出来上がったものには、こちらが思った以上に柳からダメ出しがあったが、修正を重ねながらも何とか最初の一曲が形になった。西沢君に聴かせたが、その反応を見るに、期待を上回る出来ではなかったようだ。が、バンドアレンジもまだだったし、とりあえず共作を続けてみることにした。同様に西沢君は、すでにある柳の曲にも手を入れてみたらといい始めた。流石に柳も反対すると思ったが全然そんなことはなかったから、柳の持ち曲で、個人的にもっとメロディをよくできるなと思った曲に手を入れてみた。だがこれは上手くいかなかった。完全に違うメロディに変えてみようとしたけどそれも原曲のイメージに引っ張られて不自然になった。ただ全く実りがなかったわけではなく、カバーするような気持ちで、すこしメロディーやコードを変えてみて、もっとキャッチーにしてみた曲もいくつかあり、そのなかのいくつかの細かい変更は採用された。しかし基本的にはこの期間は柳に詩だけ書いてもらったり、詩のストックをもらったりして共作を進めることになった。
思い返してみると西沢君(と僕)の思い付きに、柳もよく付き合ってくれたと思う。自分で書いてストックしていた歌詞に、彼も思い入れは絶対あるはずだし、自分だったら勝手に曲をつけられるのも嫌だし、最初の方は全然上手くいっていなかった上に、時間も沢山必要とした。この試みに疑いをもっても仕方のない状況だったが、他に何曲も完成している曲のストックがあったりしてバンドとして余裕もあったからだと思う。僕らは根気よく作業を続け、そのうちに共作作業もこなれてきて、上手くいく流れも見えてきた。まず柳が一つの歌詞のかたまり、この時点ではサビなのかAメロなのかわからない、を作りそれにメロディをつけ、柳に返す。そうすると柳が残りの部分の歌詞を作ってくる。それにはメロディもついてくる時もあるし、ついてこない時もある。それをまたこちらで手をいれ、また柳はそれを受けて歌詞やメロディーをまた変え、段々と完成に近づけていった。それは鍛冶屋が刀を鍛えているような感覚に近く、曲は回を経る度に洗練されていった。この作業を何曲か並行させて行った。西沢君は時々それを横からみて、これ以上いじくりまわすのは野暮とストップをかけたり、もう少し手を入れてほしい、とリクエストしたり、たまには彼も手をいれたりして、何曲かが完成していった。出来た曲のクオリティは正直まちまちだったが、何曲かは決してそれぞれ一人で作った時には出来ないような、我々の予想と違ったものができた。人によるかもしれないが、曲を作るときにやはり目指している方向やなんとなくの嗜好があって、そこからある程度はみ出さないものになっていくのがよくも悪くも常だった。しかし、これらの作業で産まれた共作曲はそれぞれが個別に想定し得る作風の範疇をはみ出したものになり、嬉しい誤算だった。僕らはそれらの曲がどうなっていくのか、我々をどこに連れていってくれるのか考えただけで身震いした。しかし、十月に予定していたライブまでには共作曲を形にするだけで、バンドでアレンジを施すまでの余裕はなく、結局すでに過去のライブで披露していた、三人の一番自信のある曲をそれぞれ二曲ずつぐらいやったライブになり、それらの共作曲の披露は次回、十一月下旬となった。
そのように作曲活動に打ち込んでいたころ、大学でスーツを着て黒のビジネスバッグを持った高岸が前から歩いてきて、気づかないふりをして方向転換するにも無理なタイミングで鉢合わせた。彼が何をしているのか、普段から考えていたわけではないが、就職活動をしているとは思ってもみなかった。そのまま僕の方に近づいてきて昼飯を学食で食べないか誘ってきて、就活の話を聞かされることは分かっていたし、それは自分が一番聞きたくない話題だったからいやだったが、誘われると思ってなかったから不意打ちすぎたのと、嬉しかったのもあり断れなかった。昼時で食堂は混んでおり、そのなかには就職活動中で高岸同様スーツを身にまとった後輩たちがちらほらいた。
「どうしたのその恰好」「就活だよ。わかるだろ」つまらない質問はするなよ。他に聞きたいことがあるだろ? そんな顔だった。
「バンドはやめたの? 最近きかないけど」
やっぱりそうきたか。そんな顔をして高岸はこたえた。「ああ、やめた。上手くいかなくなって。石田さんが辞めたら花田さんも辞め、続けるのも面倒になった」負け惜しみとかではなく、本当に面倒になったような、いやにあっさりとした答えだった。
「なあ。思うんだけど。もうバンドとかさ。ロックとか。終わりじゃない? よくいう死んだとかじゃなくて終わり。出尽くしたというか。ジャズやブルースみたいに古典化したというかさ。最近はバンドやりながらそんなことずっと思ってた」
「そうだな」とぼけて気のない返事で返したが、それは、石崎さんと長瀞に行くちょっと前ぐらいの時に家に引きこもりながらずっと考えていたことだった※②。2000年代のバンドミュージックに僕が期待していたのはもっと大きな物語だった。世界を大きく包み込んで一曲の上で展開してみせているような広がり。一度聴いてしまったら聴く以前の自分には戻れない様な感覚を新たにする何か。残念ながら自分は2000年代の音楽、特にバンドミュージックにそれを感じることはできなかった※③。だからこそ僕は自分たちの音楽に圧倒的な何かを求めたし、価値観にゆさぶりをかけてくる音楽を作りたかった。柳にはそんな音楽を作り出せる才能を感じていたし、それは高岸の作るものには感じられなかった。高岸は音楽の快楽原則にのっとって、観客をとにかく楽しませるような、興奮させるような術をもちあわせてはいて、それは自分にはないし、十分すごいことだったが、聴いたものの意識を変えるような、その境地には到達していなかったし、別にそこを求めてはいない気がした(だから高岸が現状のバンドミュージックに不満を持っていることが意外だった。現状のロックは快楽原則からしたら十分なものだったとおもったから)。そしてその点が自分にとって高岸を出し抜ける唯一のポイントだとし、そこを自分のバンドで超えていくことでStraySheepsの優位に立とうとしていた。だからそんな理想的な音を奏でていた絶対安全毛布に僕は激しく嫉妬した。
その場で現行のバンドミュージックについて、高岸と色んな意見を交わしたり戦わせてみたりすることはできたと思う。けれども僕は彼の持論にただ頷くだけにとどめた。彼が言おうとしている結論は「バンドをやめろ。落ち目だ。馬鹿だ。現実を見て、職を手にしろ」に向かおうとしているとわかっていたからだ。彼の服装がそれを物語っている。それから始まった話は案の定、表面上は違ったが、行間でずっと語られていることは概ねそんな内容だった。が、着地点は少し違った。
「俺も何とかバンドで世界に打って出てやろうとおもってた。そのつもりで今年は卒業せずに留年することに決めた。でも世界を変えるのはもう音楽じゃない。今やそれは企業のサービスだ。もうそんな幻想は見れない。結局はインターネットで音楽の世界すら変わってしまったし、音楽の発展もハードの歴史に縛られてる。
けど、この間のW3のライブ。良かったよ。あれを聴いて辞めた所はあるよ。だからお前は柳と続けろ。だが、悪いことは言わない、就活はやれ。バンドで食うのは難しい。仕事しながらバンドを続けてチャンスを狙え」
彼が本気で僕らにW3を続けて欲しいのかはよくわからなかった。そこからはどの様に就活をすすめるべきかのレクチャーが始まった。彼はやると決めたらとことんやるタイプだったからすでに他人に何かアドバイスできる程就活に精通していたのは不思議ではなかったが、方向転換してから直ぐにここまで戦略的に向き合えるのは異常だとは思った。こいつは本当に大学一年生の時に熱く音楽について語り合ったあの高岸なのだろうか? 別人に見えた。殴りつけて大人しくなったところで皮をはぎ、昔の高岸を引きずりだしてやりたかった。何度もいうように社会人になってもバンドを続けるなんてそんな事は考えられなかった。やるかやめるか。それだけだった。そしてやめるなら死んだも同然だと思っていた。だから彼の説得は虚しく響いた。高岸には就活について自分もボチボチ始めてみるなどといって、会社訪問と説明会に向かう彼の後ろ姿を見送ったが、実際に取り組む気はなかった。彼もその言葉をまるで信じておらず、俺は忠告したからな、という苦い顔をして去っていった。
同時期、僕は曲作りのために、時には西沢君をともなって不定期に何度も柳の家に行くようになっていたが、柳からそろそろやめてほしいといわれた。来るときはあらかじめ連絡してほしいし、出来れば二、三日前から教えてほしいと。無理もない話だと思った。僕らは共作を始めてから頻繁にあっていたし、創作の波にのっている時はいきなり西沢君とおしかけたりしたこともあった。沢山の時間を使ったし、もう柳もいい加減疲れてきたのだとおもって特に変だとは思わなかった。面と向かってやめてと言われるのはやはりショックではあったけれど分かったと返事をしてその日は早々に引き上げた。帰って欲しい雰囲気を感じたから。だが二、三日後にはもうそのことを忘れ、今しがた作った曲を脳内で再生しながら彼のアパートになんの連絡も入れずに向かっていた。途中で柳から言われた事を思い出したが、いいやと思って歩き続けた。居なかったら帰ればいいし、嫌そうだったら帰ればいい。そう軽く考えていた。柳のボロアパートは道の袋小路になっている所にあって、その道へいく角を曲がるとアパートの階段が見え、柳の部屋の入口も見えるのだが、僕が角を曲がって柳の部屋の方を見上げると、丁度扉が開き、でてきたのは柳ではなくて成戸だった。成戸はこっちを見ておらず、扉をおさえながら部屋の方をみていたので、僕に気づいたかどうかはわからない。元居た道に急いで戻り、その場を離れた。
十一月末のライブに向けて我々はスタジオでいくつか用意した共作曲に肉付けをして、最終的にこれはというものが五曲できた。そのうち心から満足できるレベルまで持って行けたのは三曲だけ。十分だった。これがW3だと胸を張って言えるような曲でどこに出しても恥ずかしくない。あと二、三曲は既存の曲を交えればライブとして形になるというか今のW3はこれだという事ができる気がした。その先の事は考えなかった。これからはその三曲の柳がリードボーカルの曲をメインとして、やっていくことになるだろう。メンバーの誰しもがそう思った様に僕には思えた。
その十一月末のライブは今までのW3の演奏の中で一番良かったんじゃないかと思う。でも四人体制のライブで一番客が少なかった。曲作りに夢中で僕らは集客に熱心ではなくなっていた。僕たちは新しくできたその三曲を、あえてきっちりと仕上げなかった。曲に余白を作り、ライブの時に偶然で埋めたかった。ライブの前に曲に飽き、演奏がおざなりになってしまうのを避けたかったのもある。「ここでやめときましょう」西沢君のアイデアだった。一曲目は今までのW3でもやっていたいつもの曲だった。全てのライブを見てる人がいるわけではないから「いつもの」と言っても観客にはわからない。結局はそれも僕らのひとりよがりだったとおもう。その後の曲は全部新曲で固めた。新曲最初の二曲は、よくよく組み立てられたギターロックで、ワイヤーとスミスとピクシーズを融合させた曲を初期のレディオヘッドがカバーしているみたいな、ポップで、攻撃的で、入り組んだ曲だった。この二曲は余白が生きる曲ではなかったから、細部をもっとつめるべきだった。出来たときは感動したし、思い入れも強かったし、客の反応も凄くよかったが、不思議なことに今はあまりピンとこない。その前にみんなが個々で作っていた曲の方がいい。ただ新曲の三曲目は違う。今でもそれは誇らしく脳内で鳴り響いている。本当に共作曲なのかというぐらいシンプルなツーコードの曲だった。サビなんてものも特にない。繰り返されるフレーズの上を歌が展開していくだけの曲だった。そういう意味では初期のW3がやっていたフォークソングに近かった。けれどアレンジと曲のもたらす広がりは全然フォークソングではなかった。この曲に関しては、もともと歌詞がちゃんと固まっており、作る前から柳の注文があった。「歌詞をこのまま使ってほしい、一文字も崩したくない」確かにそれはその塊で、一つの世界が完璧に描き出されているように、そこにあった。困ったことにそれはよくあるJ-POPのフォーマット、Aメロ、Bメロ、サビの構造は勿論のこと、洋楽によくあるヴァース(Aメロ)、コーラス(サビ)、ヴァース、コーラスの繰り返しにもぎりぎり耐えられないぐらいの短さだった。引き延ばしたり、短めの曲にしたり、数十パターン作ってもこれというのが出来なかった。形にはなったが歌詞の内容に相応しい広がりがなかったり、シンプルにイマイチだったりした。歌詞には広大な時間や空間を連想させる何かが感じられたので是非ともそのスケールを音楽的に体現してみせたかった。という事でそのような、ある種の崇高さをたたえた曲が他にないか調べ、参考にした。コードを一つか二つしか使ってないのものが多かったから、その方向で攻めることにしたところ、今までの苦労が嘘のようにすんなりと出来上がった。作っている途中からこれは凄いものになるという確信があったが、繰り返しのコード進行に耐えうるアレンジが必要で、それが難しいこともわかっていた。案の定バンドでの肉付けはかなりの時間を要し、なかなかこれというのができなかった。が、完成したものは、苦労した甲斐あって、本番で一番盛り上がるとやる前から予想できる出来だった。事実そうなった。前の曲のフィードバックノイズから緩やかにドラムがリズムを刻み始め、ベースが滑り込むように入り込む。ベースラインは曲中ほとんど動かない。だが曲のコード感とグルーヴを支える背骨の様な役割を担っていた。ずっと同じフレーズを弾き続けるのは、いくらシンプルであっても意外かもしれないが、かなり難しい。手が疲れてきてしまう。だから何時間も、何日も練習して一曲弾き通せるように訓練した。スリーピースでも事足りるようなシンプルな曲だったが、柳は歌に専念してもらい、上物のコードを定義するギターフレーズは西沢君が担当した。土台が出来上がった。踊れる曲、ダンスミュージックになっていること。それはこのシンプルな構造がずっと続くこの曲の音楽的な緊張感を持続させ、段々と高めていくには絶対必要な要素だとわかってはいたが、スタジオでの試行錯誤でそこまで持っていくのが大変だった。柳が歌う。歌詞は確信をもって発せられた。抽象的だが具体的なイメージを個々人に喚起させる、そんな歌詞だった。ライブで皆が聞き取れたとは思ってない。でも雰囲気は伝わると信じた。柳は歌と歌の合間にギターでフィードバックノイズをメインとしたソロを奏でる。やがて最後の言葉が虚空に向かって放たれると、そこから柳と西沢君のギターが解放され、その強大なノイズに含まれる神々しさで会場は満たされた。それはドラムとベースによるグルーヴで増幅され、宗教的な瞬間が訪れた。やがて全ての音が混沌の中に回収されて一つに集約され、消えていった。本当はここで終わった方がよかったかもしれない。だがまだ一曲あった。それは柳が一人で書いた新曲だった。ライブの曲順についてあまり強く主張することのない柳がどうしても最後に配置したいといったのが、この曲だった。スタジオでこれを初めて聴いた時、柳の作風ががらりと変わったと思った。口には出さなかったが成戸の影響があったのかもしれないと思った。披露された時はどちらかというとゆったりとしたビートを想定された曲だったが、西沢君は「あえて早くやりましょう」といった。僕からしてみたらこの曲は柳と西沢君の共作だと思っている。ドラムのシンプルな、駆け足のような早めのエイトビートに断続的でリズミカルなベース(シンセベースっぽい音に加工してある)、そしてその隙間にシンセがコロコロと入り、ギターは更にその隙間に控えめにカッティングを入れる。ボーカルは生活の一部分を細切れに切り取って提示していき、そこから、ちょっとした躓きや挫折が顔をのぞかせる。それも嘆きつつもそれ自体は肯定されて進んで行く。およそ大学生っぽくない曲。なぜ柳はこんな曲が書けたのだろう。今になってわかることが沢山ある歌詞だ。西沢君のアレンジのおかげで踊れる曲になったそれは、今までの柳にはなかった軽快さがあり、人懐こいメロディーに、ちょっと切なくなるような歌詞で、妙な余韻を与える曲だった。ライブの最後に位置するのは正解だったかもしれない。本当は四分半あるのに二分半ぐらいに聴こえる不思議な時間感覚があった。聴いている人の印象もやけにあっさりとしたものだったろう。最高潮の盛り上がりのなか「次で最後」と柳がいい、カウントが素早く入り、この曲が駆け抜けた。そんな歌詞ではないが、演奏中、子供が成長して青年になり、大人になっていき中年になって年老いて死んでいく、駆け足で人生を描き出した様な曲だという感じがした。
終わったあと、対バン相手で、わざわざ大阪から来ていたバンドのメンバーが興奮気味に声をかけてくれ、急だけど彼らの十二月中旬のライブに出ないかと誘われた。丁度その先のライブの予定を何にも組んでいなかったから、細かいことは考えずに二つ返事でOKをした。
このライブのあと暫く僕はふわふわした感覚が抜けなかった。なんだか少し熱っぽくて、細胞全体が喜んでいるような、ざわめいているような、そんな感じだった。それは何故か懐かしかった。
※①所謂、詞先と呼ばれる作曲法。僕もそうだったからW3は詞先で曲を作るソングライターが三人中二人もいたことになる。そういう点でも珍しいバンドだった。
※③勿論、例外や反証を集めればそれなりのボリュームにはなるだろう。だが、僕が今でも問いたいのはそのボリュームで九十年代や2010年代の音楽シーンに起こったエキサイトメントを超える事ができるのか、ということだ。僕は出来ないと思っている。