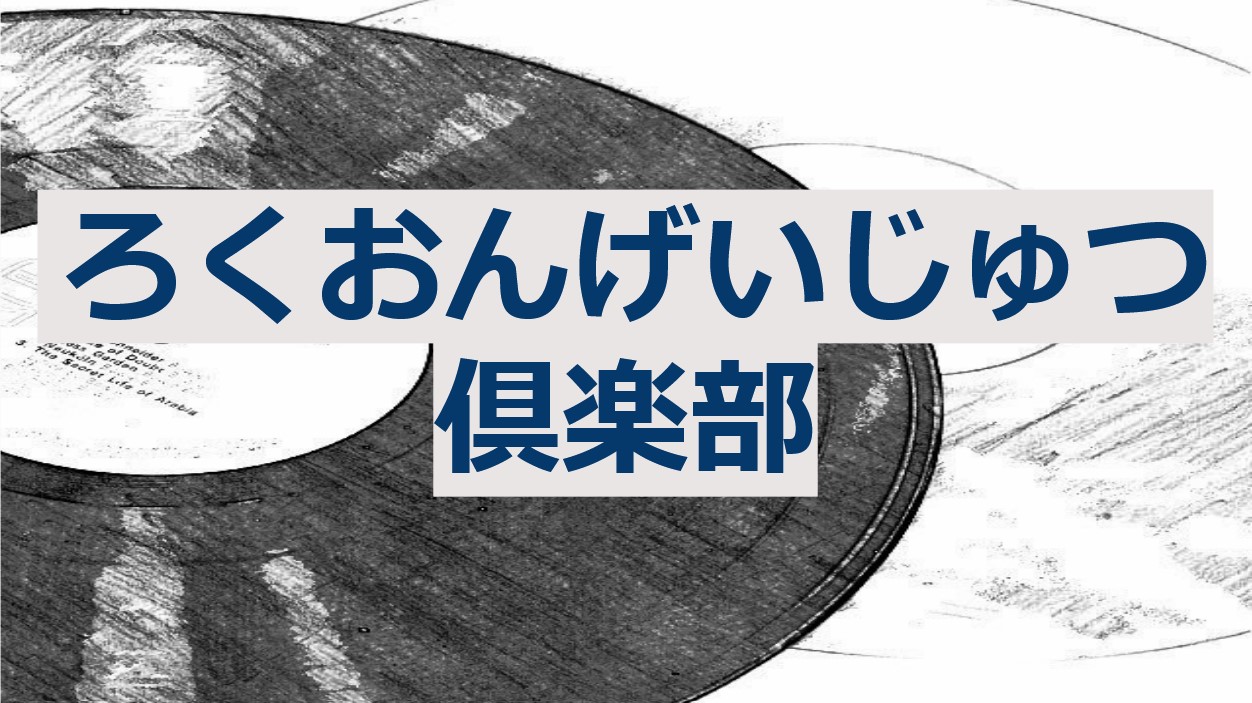高岸は律儀にも石崎さんのバンド名候補をメモし始めたので、石田さんが慌てて止めていた。石崎さんも「すまん何も思いつかなかった…」といって頭を下げた。気を取り直して石田さんが高岸のメモ帳を取ってバンド名を書いて他の三人に見せた。
・Young Boys Carrying the Stones
・Remake/Remodel
「ザッキー(石崎さんのこと)も私も名前に石が入ってるじゃん、だからstoneは入れたいなって。それから君たちのこともちゃんとバンド名に入れたいからYoung Boysを入れてYoung Boys Carrying the Stones。それから二つ目のはね、私ロキシー・ミュージックが大好きだから」
なるほど、Young Boys Carrying the Stones、カッコいいかはさておき、よく考えられたバンド名だった。少年たちに与えられた枷、みたいなニュアンスもなかなか意味深でいい。
Re-make/Re-modelはロキシー・ミュージックのデビューアルバムの一曲目の名曲でバンド名として切り取ると確かにそれっぽいカッコ良さがあった。そして何より初期のロキシーは僕たちが目指していた音楽性に近しかったし、石田さんがロキシー・ミュージックが好きと聴いて凄く納得した。※①エーテルワイズの楽曲に漂う人をくったようなユーモアやキッチュな魅力、演劇的な歌唱、テンポチェンジなどが確かにロキシー・ミュージックっぽかった。二つとも僕にはいいバンド名に見えた。「リメイク/リモデルはともかく最初のはなげーよ」と石崎さんが言った。続いて高岸が出しにくそうにメモに書いたのが下記のバンド名だった。
・Burning With Optimism’s Flames
・Tiger Lilywhite
「これも長いね」と石崎さんは笑った。「上のはXTCの曲のタイトルです。したのはピーターパンに出てくるタイガーリリーからです。それだけだと面白く無いのでリリーホワイトにしました」「※②スティーヴ・リリーホワイトだ!」僕より早く石田さんが反応した。
僕の番がきた。なんだか自分でバンド名を口に出していうのが恥ずかしかったので僕はバンド名を書き殴ったメモをそのままテーブルにだした。
・The Great Escape
・すとれいしーぷす
「すとれいしーぷすいいね、平仮名なのがかわいい」と石田さんが言ってくれたので、平仮名なのはスペルを忘れてしまったからという説明をし損なってしまった。
という事で全ての候補が出揃った。
・Young Boys Carrying the Stones
・Remake/Remodel
・Burning With Optimism’s Flames
・Tiger Lilywhite
・The Great Escape
・すとれいしーぷす
何かを一つ選ばなくてはならない場面で、ひとつだけフォーマットが違うものがあると、それがアリかナシかを議論してもらえるから有利である、という様なことを何処かで読んだことがある。出来上がったリストに英語が並ぶ中、平仮名の「すとれいしーぷす」は非常に目立った。そして平仮名のバンド名も「はっぴいえんど」みたいでいいねという意見もあり、結局バンド名は「すとれいしーぷす」となった。
テストとレポートがあるから、という事で、次の練習は三週間後の七月の終わりになった。その場で石崎さんがスタジオの予約をとってくれた。やる事が多そうだったので長めの三時間だ。
カフェを出るともう五時近くで、まだまだ明るく帰るには早い時間だったけれど楽器を背負った僕たちにはCD屋ぐらいしか行く体力がなかった。けどみんなCDをディグる気分でも無かったのかそれぞれの帰路についた。
さて、ここで一つ僕の音楽遍歴を語る上で非常に重要な出来事を語ろうと思う。それは今までイギリスのロックミュージックを中心に音楽を聴いてきた僕にとっては、正に地殻変動とでも呼べる様な出来事だった。そしてその事を語るにはまずバイトの話をしなければならない。
僕たちの親は幸運な事にその働き盛りの時代をバブル景気と共に過ごしていた。だからそれなりの蓄えがあった親が多かったのかもしれない、そんなわけで僕や周囲の人間の多くはバイトをしなければ生きてはいけない、という程には追い詰められてはいなかったが(勿論そういう人もいた、だが今みたいに多くは無かった)、それでも仕送りだけでは生活を切り詰めずに充実した生活を送るためにはアルバイトが不可欠だった。ましてやバンドという非常に金がかかる活動をしている場合なおさらだった。英米のロックレジェンド達がバンド演奏で小銭を稼ぐ、などという状況からは遠く離れていた。結局の所、日本は音楽文化が欧米ほど身近なものでは無かったし、バンドはもうお金にならないという事を当時見抜けていなかったのが僕たちの敗因だったと思う。僕たちはCDバブル時代の子供達だったし、※③97の世代と呼ばれるバンド達の影響力も凄まじいものがあった。バンドという音楽形態にはまだまだ明るい未来があると思っていた。
話が逸れた。アルバイトだ。僕はモデルルームの看板持ちのアルバイトをしていた。新興住宅地の建築予定地にあるモデルルームへの立て看板を持って、会場へと案内するバイトである。要は会場への案内の看板を道路沿いに設置したりするとかなりのコストがかかる。そこで、訪問者の多い土日限定で人を要所要所に配置して看板を持たせて会場への案内をさせるということである。話題にはしていなかったが英語のクラスでの同学年の友達が僕にも何人かいて、その中の一人に紹介してもらったバイトだった。という事で僕は人生初のアルバイトがそれで、五月の中旬から土日にちょくちょく仕事を入れていた。一番最初の現場は横浜線の沿線の駅の一つだった。交通費は全額支給ではなく千円ぐらいまでだったので家から遠い現場の時は交通費のあしがでてしまうのだが、よくも悪くも金銭にあまり注意を払っていなかった僕はこんなものだと思っていた。それよりも全く未知の東京近郊の様々な場所に行けるのが田舎から上京してきた僕にとってはなかなか楽しかった。その最初の現場で出会ったのが高良くんだった。
その日の現場である横浜線の駅には朝九時集合だった。今はコンプライアンスの関係などでそうではないと思うのだが(そう、信じたい)、モデルルームの看板持ちのバイトは、どんなに暑い日でもスーツの着用義務があった。当然ネクタイも。その時はまだ五月だったので暑かったけどまだまだ耐えられる範囲ではあった。仕事がはじまるのは十時からだけど、駅前からモデルルームまで歩いていき、そこで肝心の看板などを受け取り、その後所定のポジションにつかなければならないので、九時集合だった。時給が発生するのは十時からで、九時集合の義務があるにもかかわらず、十時までは無給だった。時給は千円だったと思う。途中休憩が一時間あって十六時までの勤務で実働五時間だから一回入れば五千円貰える計算だ。実質拘束時間の長さや、後で詳しく書くがその内容の辛さを考慮すると正直アルバイトとしては全くオススメ出来ない。スーツを着るのは入学式以来で、ネクタイをしめるのに時間がかかってしまい、僕が駅に着いたのは九時ギリギリだった。
僕以外のメンバーは全員到着しているみたいで、リーダー格の人が時計を見ながら険しい表情で僕を一瞥して僕の名前を確認すると僕たちの雇い主に電話で全員が揃ったことを報告した。記憶が朧げだけれども確か家を出発するときにも電話報告が必要だった気がする。リーダー格の男は僕よりも少し小柄で三十代半ばの男だった。「君、靴」と彼が僕に言った。「あっ」慌てて家を出てきたために僕は革靴ではなくいつもの癖でスニーカーを履いてきていた。※④ブロンディの『恋の平行線』のジャケットみたいな格好になっていた。「次から気をつけてね」というと彼は「じゃついて来て」と言って先頭を歩き始めた。僕はスニーカーで来てしまったことで一日中ブルーな気持ちで過ごすことになりそうだった。
駅前にはこぢんまりとしたロータリーがあってバスやタクシーが並んでいた。後で知ったが駅の反対側はもっと開けていた。しかし、僕らが集合した側は低い建物とごちゃっとした商店街が少しある落ち着いた街並みで、そこを抜けると整備された広い道路に出た。道中顔見知りの連中は楽しそうに会話していたが、僕は最後尾をとぼとぼと足元のスニーカーを見つめながら歩いていた。その目の前を背の高い短髪の男が歩いていて「気にすんなよ。オレも最初スニーカーで来ちゃったから親近感湧いたよ」と信号待ちで僕が皆に追いついた時、笑いながら小声で話しかけてくれた。それが高良くんだった。
高良くんは八王子の多摩の森の中にある私立大学の二年生で年上だったけど「敬語とかめんどくせーからタメでよくない」と言ってくれた。話を聞くとこのバイトは六回目ぐらいで、お金が必要なときに適当なタイミングで本業のバイトとは別でちょくちょく入れているという。「欲しいもんがあってさ、ターンテーブルとミキサー買おうと思って、そのためにお金貯めてんのよね」「え、DJとかやるの?」「いや、まだやってないけどやろうかなと思ってさ、一応ラップはやってるんだけど」
この時「じゃあちょっとラップやってみてよ」と言わなかった自分を褒めてやりたい。僕はその言葉を飲み込んで聞いた。「どんな音楽聴くの」「ソウルとかR&Bも聴くんだけどやっぱりメインはヒップホップかな」僕は自分はバンドをやっていてメインはロックリスナーである事、そしてソウルは少し聴くけど※⑤ヒップホップはRUN DMCとかLL Cool J、ビースティー・ボーイズや、エミネム、パブリック・エネミーしか聴いたこと無いと話をした。
「もっと聴きたいと思ってるんだけど、英語が分からなくていまいちのめり込めないのかも」「でもバンドやってる人にしては結構聴いてるし十分じゃない。日本語ラップは?」「※⑥ドラゴン・アッシュとかリップ・スライム、キック・ザ・カンクルーしか聴いたことないんだ、後はスチャダラパーとか」「まぁそうだよね。実際俺も好きだしね」と言って彼は笑った。
「コーラだ」
「えっ?」
「名前だよ。高良。高いに良いでこうらって読むんだ。よく飲み物と間違えられる」
少し笑って僕も自己紹介をした。今なら高良くんは高良健吾の高良ですって言えばいいわけだ。高良くんがそのように自己紹介するのをみてみたかった気もする。
肝心のモデルルームの会場にはもうすぐ着くだろうと思ったタイミングから更に十五分ぐらい歩いてやっと着いた。結局三十分ぐらい歩いた。その頃には辺りは建物が少なくなり、ポツポツと新築の家があって後はほとんど更地だった。そしてその更地には全て立て看板があって、これからそこに何が出来るのかを説明していた。そこは東京ではなくもう神奈川だったが、東京近郊にこんな開けて何にもない場所があるのが驚きだった。再開発の結果なのかも知れないし、つい最近までは森だったのかも知れない。問題のモデルルームは大通りを曲がって三百メートルぐらいした少し小高い丘の上にあった。「こんな駅から遠い所のマンションなんて売れるのだろうか」と疑問に思ったが建設予定のマンションのチラシを見て納得がいった。駅前まで住人の為のシャトルバスを運行する予定だということだった。一応バス停も大通りには存在していた。例のリーダー格の人がモデルルームに入っていってスーツを着た営業マンと談笑しながら一緒に出てきて営業マンが物件についての簡単な説明をして、建築予定の物件のチラシを皆に渡した。営業マンがチラリと僕の靴を見た気がした。五分ほどタバコとトイレ休憩があって、例のリーダー格の男と営業マンが屋外の喫煙コーナーでタバコを吸っていた。それをみると高良くんも無表情で近づいていって一緒に吸い始めた。高良くんがいつも吸っていたのは※⑦キャスターマイルドで、僕はキャスターマイルドのあの独特のどこか食欲を刺激するような香りを嗅ぐと今でも高良くんを思い出して懐かしさで胸が苦しくなってしまう。休憩が終わると僕らはモデルルームにある資材置き場みたいなところに連れて行かれ、それぞれの立て看板とパイプ椅子を手渡された。僕たち看板持ちのバイトグループは全部で6名だったと思う。例のリーダー格とは別にもう1人40代ぐらいのおじさんがいて、後は学生かフリーターっぽい感じだった。全員男だった。リーダー格ともう1人僕らより少し年上ぐらいの若い男がベテランっぽい雰囲気を醸し出していて、2人とも看板ではなく、大きな紙袋を2、3個持っていた。「ではそろそろ出発します、よろしくお願いします」と無駄に大きな声でリーダー格が営業マンに言って、僕たちは看板とパイプ椅子を持ってぞろぞろと来た道を戻り始めた。
※①今はこうやって辛うじて言語化出来ているが、当時の僕がこの様に言葉にできていたわけでなく、「あの感じロキシー・ミュージックと言えばそうだな」、と感じていただけである。石田さんはロキシーを因数分解的に分析していたから、もっと突っ込んで言語化できるに違いなかった。
※②スティーヴ・リリーホワイトはイギリスの音楽プロデューサー。ピーター・ゲイブリエルやラーズ、U2、そしてXTCのプロデュースで知られる。
※③ナンバーガール、くるり、スーパーカーの97年にデビューしたバンド達のこと。実際には97年と定義していいのか怪しい部分もあるけど、まぁ便利な言葉なのでそのままつかった。そしてたしかに、その3バンドが2004年当時相当影響力を持っていたのは肌感覚としてあった。特にナンバーガールはすでに解散していたものの、ライブハウスには彼らの影響を受けたバンドがうじゃうじゃしてた。スーパーカーは翌年の2005年に解散。くるりは『アンテナ』を発売したころだった。
④ブロンディはデボラ・ハリーを中心とするアメリカのニューウェーブバンド。『恋の平行線』(Parallel Lines)は彼らの代表作で白いドレスのデボラに他のメンバーがスーツなんだけど足元は何故かスニーカーでメンバーが並んでいるアルバムジャケットである。ブラーがこれのパロディのアー写を撮っていて、ボーカルのデーモンが女装している。自分のミスを正当化するつもりはないけど、スーツにスニーカーは結構カッコいいと思う。
※⑤当時のロックリスナーのヒップホップの入り口の多くはビースティー・ボーイズやエミネムだったと思う。ただ僕もそうだけどそこから先に進んでもっとヒップホップを聴いてみようという人は少なかった気がする。僕もそうだった。が、よくよく考えてみたら、リンキンパークにはマイク・シノダがいたし、リンプ・ビズキットもフレッド・ダーストがラップしていたし、Kornはヒップホップのリズムをベースにしていた。そしてそんな彼らの源流であるレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンもメタルとヒップホップを掛け合わせた斬新なサウンドを90年代にもたらしていた。ただ僕は彼らがヒップホップの影響を受けていたことについて真剣に考えていなかったんだと思う。
※⑥よくよく冷静に考えてみるとお茶の間にヒップホップを届けていた彼らを僕はヒップホップだと思って聴いていたわけではなかった。ヒット曲の一部としてごく当たり前に聴いていた。それほど彼らの作っていた音楽は聴きやすく、スッと懐に入り込んできていた。でもそこからヒップホップを掘り下げる事も僕はしていなかった。何故だろう?
※⑦因みに彼は香水、サムライもつけていた。サムライはアラン・ドロンが三船敏郎をイメージして作った香水である。このサムライの香りも彼を未だにおもいおこさせる。