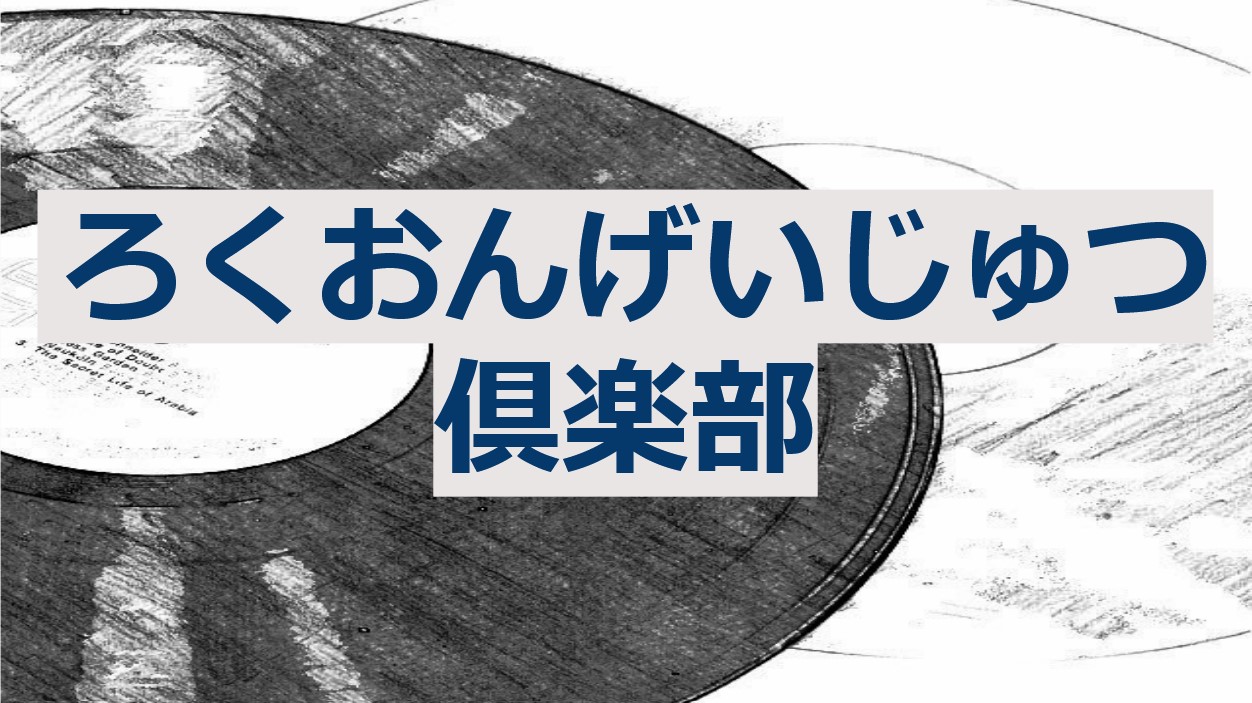以前Music magaine誌の邦楽アルバムベスト100という企画を当サイトでも取り上げました。
そのランキングを見て「自分だったコレをいれるなー」とか、「これはもっと順位高いなー」とか考えてたら、いてもたってもいられなくなり、
今回自分でも邦楽アルバムベスト100をやろうと思いたちました。
それから約5ヶ月間…
作業を続けてやっと形になったので、
当サイトでも邦楽アルバムベスト100発表します!
選考基準
選考にあたっていくつか自分でルールを決めたのでまずはルール説明から。
ということで下記の条件に当てはまるものを選出していきました。
1. 1960年代から現在(選考を開始した2019年3月)までに日発表された邦楽アルバム。
2. 編集版、ミニアルバムを含むが、複数のフルアルバムから曲を集めたベスト盤は選考対象外。
3. 1アーティスト3枚までランクイン可。
4. 歴史的背景や影響力もランクの上下に加味されるが、結局はアルバムを聴いて自分がどう感じたかを優先。
1、アルバムという形式が単なる曲の寄せ集めではなく、一つのコンセプトをもった作品たりうる、そういう認識が持たれ始めた時代から現在までを対象
具体的にはフォーク・クルセダーズの名盤『紀元貳阡年』が発表された1968年からですね。
2、ベスト盤は基本選出外
ベスト盤をいれたらベストばっかりになってしまう可能性もありますし、時代性もみえてこないので基本はずしました。
ただし、インディーズ音源を集めたものや、フルアルバムからでなく、ミニアルバムやシングルのみを編集したベスト盤、企画盤はOKにしました。
また、シングル盤は選外ですが、ミニアルバムはアリとしました。
3、 1アーティスト3枚まで
やはり筆者が個人的に好きなアーティストは沢山ランキングにいれたくなります。しかし一つのアーティストが極端にランクインしすぎるとつまらないランキングになってしまうので、1アーティスト3枚までの縛りを設けました。
4、歴史的評価に比重を置きすぎない
日本のポピュラー音楽史でこれは絶対にはずせないという影響力をもったアルバムがいくつか存在します。しかし、そんなものばかりをいれていたら、他のランキングと似通ったものになってしまい、面白くありませんので、極力排しました。
ただその歴史的な影響力と筆者が「良い」と思った部分が重なっていれば全然かまいませんでので、そういうアルバムはランクインしています。
ただ世間、評論家筋の評価が高いからという理由ではランクインさせませんでした。
ですのであたりまえですが、出来上がったランキングになんの権威性もありません。主観の塊です。
上記の理由から本来こういう企画には絶対に入ってしかるべき名盤たちも選外だったりします…。
まぁその批判に対する回答や言い訳は後々詳しくやっていこうかなと思っています。
以上を踏まえて早速紹介していきます。
100位 globe 『globe』1996年

当時絶好調だった小室哲哉が全てをつぎ込み 400万枚以上を売り上げ当時の売り上げ記録を塗り替えたメガヒットデビューアルバム。
いま聴くと時代を感じる音像で音圧も不足している感は否めないですが多幸感溢れる楽曲の瑞々しさは変わらないと思います。
globeは小室哲也とボーカルのKeiko、ラップ担当のMarc Pantherの三人からなるユニット。
いまあらためて聴いてみるとマークのラップってマークのラップって、曲によっては本当に装飾に徹してるところがあって面白いですね。
セルフボースティング (「俺はスゲェ」などと自分自慢をすること)でもないし、パーティラップみたいなただ楽しい感じでもないですし、ひたすら状況説明というか物語の盛り立て役というか。
当然日本のHipHop界隈ではスルーされていたと思いますが、こういう感じのラップのあり方がそれ以降のJ-popにも引用されたりして、そういう影響力はあったんだなと思いました。
あと小室哲哉のコーラスの入れ方ってメロディのクセのせいかも知れないけど気持ち良さ追求したものじゃなくて、独特の変な質感を生み出すようなマニアックなハモり方で面白いです。
おすすめ曲
Aメロの明るいメロディからだんだんとダークになっていくのがくせになる「Joy to the Love」。ポップで弾けるメロディがサイコーな「Sweet Pain」。切なさと楽しさがいい塩梅でミックスされたデビュー曲「Feel Like Dance」。
99位 Hi-STANDARD『MAKING THE ROAD』1999年

ポップでキャッチーで盛り上がる曲がたっぷり詰まったパンクの名盤。
昔は学園祭でハイスタをコピーしてるバンドが1組は必ずいたという、直撃世代にとってはもう青春の一ページを飾った忘れられない一枚。
日本のパンクを語る上ではずせないアンセム「STAY GOLD」収録。
98位 B’z 『RUN』1992年

打ち込みメインの音作りをやめ、ハードロック趣味、バンドサウンドを全開にした一枚。
しなしながら良い意味で歌謡曲的だったりして、なかなかそういうのは洋楽では味わえないですよね。
冷静に考えると結構変なユニットだなと思います。
おすすめは「THE GAMBLER」「さよならなんか言わせない」「Baby, You’re my home」。
3曲ともベスト盤などには入っていませんが隠れた名曲。
ベスト盤常連の「RUN」「ZERO」も収録。名盤。
97位 チャットモンチー『耳鳴り』2006年

徳島出身の3ピースバンドのデビューアルバム。
初めて聴いた時は「凄いバンドが出てきたぞ!」と興奮したのを覚えています。
それぞれの楽器が隙間を埋めるような退屈な演奏をしているのではなく、それぞれの楽器が曲をちゃんと盛り上げようと工夫しているのがいいんですよね。
また全員がなんらかの形で作曲に貢献しており、それがバンドの楽曲に幅と深みを与えているところがポイント高いです。
おすすめ曲
上京したての若者のナイーブな心情をつづり、彼女自身にも重なる「東京ハチミツオーケストラ」。サビの切実さが胸を打つ「さよならGood bye」。
96位 PERSONZ『PERSONZ』1987年

今回のランキングの中で正直一番時代を感じるアルバムかも知れません。
しかし、本田毅のエフェクトがかかりまくったギターが好きだし、勢いのあるこの当時の特有の元気なサウンドと切なさがたまらない一枚。
おすすめ曲
バンドの勢いがいい感じでパックされた名刺代わりのオープニング曲「Midnight Teenage Shuffle」。エンディングのもうひと展開がたまらない「Burnin’ With Love」。
95位 ほぶらきん『ランニングホームラン』1980~81年

コミックバンドともとられるような面白い楽曲がめちゃくちゃなテンションで演奏されているアルバム。
僕はパンクだと思ってます。
アマゾンのレビューでボロックソに酷評されてるアルバム(笑)。
けれど、「こんな曲でもいいんだ」「自由でいいんだ」って思えたし、実際聴いてから筆者もすぐに曲を作り始めました。
「音楽やバンドってこうでなくてはならない」とか「格好つけてないとだめ」とか変なメンタルブロックをぶっ壊してくれる音楽だと思ってます。
94位 りりィ『Dulcimer』1973年

70年代を中心に活躍していたシンガーソングライター。
近年では女優として活躍していましたが、惜しくも2016年に亡くなりました。
ハスキーボイスと情感のこもった歌が魅力です。
おすすめ曲
彼女の代表曲で、1番有名な「心が痛い」。エデンの園追放譚をモチーフに少女の性への目覚めへの葛藤、戸惑いをテーマにした「りんごを食べないで」。りりィの掠れたハスキーボイスが切なさを際立たせる振られ系ラブソング「変型ねつかれなくて」。
93位 LÄ-PPISCH 『LÄ-PPISCH』1987年

2つのバンドが合体してできた実力派集団のデビュー作。
「タンポポ (Toys2)」「パヤパヤ」という二大名曲だけでも聴きどころ十分なアルバムです。
スカとパンクを基調としたカッコよくて楽しい楽曲の宝庫。意外とメッセージ性も強い。
おすすめの曲
全てのパートがめちゃくちゃ恰好よく、LÄ-PPISCHのバンドとしての魅力を理解する上で最適の入門曲「タンポポ (Toys2)」。楽しくてカッコよくて踊れる代表曲「パヤパヤ」。
92位 The Boom 『Lovibe』2000年

アルバム毎に音楽性をかえ、結構挑戦的なことをやってきた彼ら。
このアルバムはそんな冒険から一息ついてリラックスしたムードで作られた様な一件地味なアルバムですが、やってきた事をコンパクトに落とし込んだ完成度の高いアルバム。
おすすめの曲
スティール・パンやボサノバ的リズムなどを導入した南国感のあるさわやかなナンバー。夏に涼しい部屋でリラックスして大事な人の事考えながら聴いたりしたい「子供のように」。多幸感あふれるラブソング「天に昇るような気持ち」。シンプルにカッコいいロックなラブソング「I’m in love with you」。「この街を出て行こう 電話帳の中から抜け出そう」「神様以外は呼び捨てにしてる」とか詞も良い。ポエトリーリーディングを全面的に取り入れて作った「手紙」とかでやった実験とか、ソングライティングとか、詩作とか、今までやってきた事を肩の力を抜いてすっと落とし込んだような名曲「いつもと違う場所で」。
91位 NUMBER GIRL 『SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT』1999年

20世紀の最後に、バンドという形態がまだ有効であると言うことを強力に示してくれたバンド。
彼らの登場からライブハウスにいくつも影響を受けたバンドが現れたことか。
ただライブ盤の『記録シリーズ』やライブ動画とかみてしまうとスタジオ盤がなんだか物足りなく思えてしまって、それで低めの順位に。
おすすめの曲
「透明少女」疾走感あふれる代表曲。ZAZEN BOYSと比べるとナンバガの詩は全然練られていない感じはどうしてしてしまうが(ライブでも歌詞を忘れてテキトーに歌われたりもしますし)、「はいから狂い」とか「桃色作戦」とかその歌詞の独特の表現はここでも健在。要はファッションに夢中で自分達をカワイク魅せたい女の子達を「はいから狂い」とか「桃色作戦」っていうフレーズで表現しているんですけど、これが説明的な文章と「歌詞(詩)」との違いですね。
「EIGHT BEATER」。「ああ、夏はあつい」で始まるアルバムラストの楽曲。冒頭でスネアドラムのスナッピーが共鳴していることからもバンドで一斉に録音していることがわかります。このライブ感がナンバガのスタジオ盤の魅力なんでしょうね。逆に言うと緻密な音作りやスタジオワークには積極的ではなかったことにもなります。
まとめ 100位から91位
と、駆け足で100位から91位まで紹介していきました。
大体どんな邦楽ロックベスト100などのランキングでも10枚ぐらい選ばれているものを見れば、「こういうスタンスの選盤なのね、じゃあ上位はあのアルバムとか入りそうだな」というのが見えてくると思います。
が、当サイトのランキングはどうでしょうか。
結構節操のないランクに仕上がっているので、まだ見えてこないのではないのではと思っています。
ということで90位から81位に続きます。
90位 電気グルーヴ『A(エース)』1997年

電気グルーヴ最大のヒット曲である「Shangri-La」収録。「お馬鹿」と「真面目」とがいい塩梅で調合されたバランスのよいアルバムで、そういう意味で初心者にも聴きやすいアルバムでもあり、彼らにしか作れないアルバム。このアルバムを最後に砂原良徳が脱退。
おすすめの曲
「猫夏」石野卓球、砂原良徳の共作。シリアスなトラック。リズムが入るところがとにかくカッコよい。「ポケット カウボーイ」ピエール瀧作詞、石野卓球作曲。さくらももこ原作のアニメ『コジコジ』の主題歌。電気らしいユーモアとポケットカウボーイの孤独と哀愁がミックスされ、ここでしか味わえないテイストがある。「SMOKY BUBBLES」石野卓球作詞、石野卓球、砂原良徳作曲。アンビエント的な落ち着いた楽曲。らしくないといえばそうなのかもしれないが、凄く穏やかな気分になれる楽曲で、彼らの音楽性の幅広さを示す一曲。
89位 松任谷由実『NO SIDE』 1984年

寒い季節に重宝しそうな「冬」を感じるアルバム。ストーリーテリングの巧みさと楽曲の良さ、バックを務めるミュージシャンの確かな演奏が光る一枚。しかし、この時代がまといつつあった、ある種バブリーな雰囲気と、人生の軽やかさに、2019年との距離を感じますね。もう違う国の物語の様に響く時がある。僕はたまたま縁があってリアルタイムでも無かったのに聴いていますが、若い世代が共感できる内容とは思えないといったら大げさでしょうか。
おすすめの曲
「ノーサイド -No Side-」 これを書いている2019年10月はラグビーワールドカップ日本開催で盛り上がっていますが、ラグビーの曲と言ったらこれしか出てきません。合が終わったら敵味方はないという「NO SIDE」という言葉もこの曲でしりました。
「DOWNTOWN BOY」 いわゆる「不良」の男の子と「普通」の女の子のラブストーリー。視点は女性側からのもの。優れたストーリーテリングが発揮される名曲。余韻のある終わり方もいい。恋人たちには離れた後もそれぞれの人生が待っていることを強烈に感じさせる一曲。
「午前4時の電話 -A 4am Phone Call-」 はじめて聴いたときはあまり印象にのこらなそうな曲ですが、好きです。別れた恋人が午前四時に電話をよこすという内容なのですが、当時ならではじゃないでしょうか。いまではスマホが主流なので、夜邪魔されたくなければ電源を落とすとかでいいとおもうんですよ。あと連絡もLineとかできそうじゃないすか。「いまいい? 起きてる?」とか言って。けど当時は固定の電話しかないから、否応なしに電話のベルで起こされちゃうわけです。そういった時代背景や、午前四時という時間設定を踏まえると、電話をかける方の心情が見えてきますね。
「一緒に暮らそう -Let’s Move In Together-」 プロポーズソング。多幸感あふれるスウィングナンバー。さよならをいわなくてもいい方法→いっしょに暮らそう、というわけです。
88位 坂本龍一『千のナイフ』 1978年

渡辺香津美の最高に熱いギターソロが聴ける「Thousand Knives」「The End of Asia」という2曲の必殺の名演を収めたYMO前夜のソロデビュー作。この2曲は後々YMOでも披露されるのですが、本アルバム収録のバージョンの方が断然よいと思います。
おすすめの曲
「千のナイフ Thousand Knives」 最初の一分ぐらいは毛沢東が井崗山(せいこうざん)を訪れた時に詠んだという詩がヴォコーダーを通して朗読される。そのせいもあるのかも知れませんが、琴などの音色や、使用している音階などから中国っぽい雰囲気がこの曲にはあります。中国で、仙人がすんでいそうな切り立った細い山々が霧の中にたたずむ景色の中をボートで移動しながらこの曲を聴くのが夢ですね。これはアジアっぽい、ごちゃごちゃした生活観のある町並みや市場で聴くと感動するので是非試して見てください。聴き所は前述したように渡辺香津美の熱いギターソロ。YMOのバージョンは原曲の持つ不穏な要素を活かした不気味さが光るダークな電子音楽になってます。
「The End of Asia」 「千のナイフ Thousand Knives」と対になる名曲。この曲でも「アジア感」は健在ですし、渡辺香津美のギターソロが圧巻。
87位 YMO (Yellow Magic Orchestra)『浮気なぼくら』 1983年

優れた音楽家集団が全力でポップソングを作っちゃいましたな名作。惜しむらくは「以心電信」が予告編的なショートバージョンでなく正規のバージョンで、「カオスパニック」が入っていたら…。直撃世代は「ライディーン」とか初期のYMOの方をこのまれる傾向にありますが、僕は歌もの中心のポップな後期派です。この頃のYMOでいきなりサビから入るパターンの曲が結構あって、最初にうわーって盛り上がる感じも好きだったりしますね。YMOのポップソングって、割と精神的にまいっている時、疲れている時でも聴けるっていうか、逆に良いっていうのが不思議ですね。曲がある種の憂いを帯びてたり、制作側が当時病んでたことも関係してると思います。
89位で取り上げたユーミン(主に松任谷由美時代)のポップソングとはまた違うなと。ユーミンは元々ベースでハッピーな人達が更に豊かな生活を求めて聴くための曲っぽいところもあるような気がしますね。
おすすめの曲
「ONGAKU/音楽」 教授(坂本龍一)作詞作曲。ソロも当然最高なのですが、ビートルズにいたときのジョージが好きみたいな感覚で僕はYMO在籍時の教授が好き。特にYMO後期の作風が好きですね。娘の坂本美雨のために書いた曲で、メンバーの三人が交互にボーカルをとったりする場面もあったり実にほほえましく、やわらかい楽曲です。
「KAI-KOH/邂逅」 これも教授作詞作曲の曲で、メインの歌は高橋幸宏。こちらも88位の『千のナイフ』でも言及したような、中国の大陸的な雰囲気で広がりのある楽曲で、そのエッセンスを上手くポップソングに落とし込んだような作品。
「EXPECTING RIVERS/希望の河」 高橋幸宏作詞、高橋幸宏、坂本龍一作曲。ボーカルはユキヒロさん。三人の中でボーカリストとして1番好きなのはやはりユキヒロさんですね。タイトルに希望とあるように、かなり明るい雰囲気の曲調ですが、ブリッジの部分、「時々闇夜に漂う僕、手探りで流れてた僕ら」でダークな要素を入れてきます。全部明るいんじゃなくて、こういう部分が楽曲にあるのがいいですね。
「WILD AMBITIONS」 細野晴臣作詞、細野晴臣、坂本龍一作曲。YMOで唯一この二人きりで取り組んで共作した曲らしいです。それもそのはず、教授と細野さん、当時二人はめちゃくちゃ仲が悪かったらしいですね。最近は全然そんなこともなく結構競演しているので二人のファンとしてはうれしい限り。
86位 マジカル・パワー・マコ『マジカル・パワー』 1974年

ドナルド・ダック、ケチャ、津軽三味線、…様々なコラージュ、音楽が渦巻く一大絵巻のようなデビューアルバム。作曲家武満徹が絶賛した才能を是非。人を食った様なジャケットもシンプルでかっこよい。マジカル・パワー・マコは静岡県伊豆市の修善寺町出身。僕も2、3回行ったことのある山村の観光地なんですが、温泉はもちろん、その名の通り寺あり、明治に建てられた古い教会ありでなかなか面白い環境です。上京後の作品故に影響がどの位なのか、邪推しか出来ませんが、お越しの際は是非お手元にこのアルバムをば(笑)。
おすすめの曲
「チャチャ」インドネシアのバリ島の民族音楽、ケチャを取り入れた楽曲で、ケチャの合間に様々な音のコラージュが入るなかなかに前衛的な作品。初めて聴いたときは衝撃でした。
85位 Mr. Children 『Kind of Love』1992年

2ndアルバム。前作がミニアルバムだったので、今作が初のフルアルバム。
まだ大ヒットを連発する前の初々しさがありますが、プロデューサーの小林武史の助けもあって、ソングライティングは既に完成されており捨て曲が無い名盤。
ミスチルという文脈から完全に切り離してアルバムだけをただ単体で評価したらもっと上位な気が…例えば名も知られぬバンドがたった一枚だけ残したのがこれだったら…もっと正当な評価が得られて異なる層に愛されたのではと思わずにはいられないです。
そういう意味ではミスチル最高傑作。
84位 水曜日のカンパネラ『私を鬼ヶ島に連れてって』2014年

じいちゃんMountain芝をCut! 婆ちゃんRiverでWash! 収録曲「桃太郎」がタワレコで流れてきたとき、衝撃を受けました…。なんじゃこりゃ…。数少ない店頭で流れてるのを聴いて即購入パターンの1つ。これなんですか?って聞くの恥ずかしかったですが、買って良かったです。歴史上の偉人をキーワードにして展開していく世界も新鮮でした。
コムアイのラップとも歌とも取れる様な歌唱は、ちょっと舌足らずな感じもあり、普通のラップとかだったらアウトなのですが、それがかえって味になっていて魅力的なんですよね。あとは歌詞の内容は駄洒落だったりするんですけど、音がシリアスだったり、言葉の音韻や響きやリズムのよさを重視しているので、コミックソング的な消費をされず、何回でも結構聴けてしまうんですよね。
おすすめの曲
「千利休」 「桃太郎」と双璧をなす曲で基本的な歌詞のアイデアも一緒。千利休の歴史的事実よりもお茶を軸にして現代的事象を絡めた歌詞になってます。
「チャイコフスキー<Interlude-ラモス->」「千利休」や「桃太郎」よりもチャイコフスキー要素は薄く、ロシア関係の事象や「スキー」からの連想が中心となる曲。広瀬香美やJRの昔のPRの文言など、古い話題やキーワードが多いのも特徴。「桃太郎」でもPCエンジンやメガドライブ、高橋名人などが登場する。
83位 かせきさいだぁ『かせきさいだぁ≡』1995年

デヴィッド・ホックニーみたいなジャケの中身は、梶井基次郎などの日本文学やはっぴいえんど界隈を中心とする音楽を下敷きにした極めて「邦楽的」ヒップホップ。通常のヒップホップの文脈とはやっぱり違って韻音よりも、詩としての響きの方が優先されているので、ヒップホップ、ラップ好きからは、これはラップじゃないといわれそうではあります。どちらかというと歌やポエトリー・リーディングに近いスタイルの曲もあります。あとは前述したとおり引用もとが「洋楽」でなくて「邦楽」メインなんですね。その点もかなり異質であり、象徴的かと。共に露骨にはっぴいえんどを参照、意識したサニーデイ・サービスの『若者たち』も本作と同じく発表は1995年。同時代というのは興味深いですね。
おすすめの曲
「さいだぁぶるーす」 1曲目。自身の名の一部を冠した曲でもあり、かせきさいだぁの世界観が理解できる名刺がわりの一曲。
「相合傘」 イントロは鈴木茂の「ウッドペッカー」のサンプリング、タイトルははっぴいえんどの曲名からでしょうか。歌詞にも鈴木茂の曲の引用があります。聴いていただければわかるようにラップのようでいて全然韻を踏んでないんですね。間奏部分では梶井基次郎の小説『城のある町にて』の一説を引用。
「じゃっ夏なんで」 これ以上夏を感じさせる曲って中々無いと思います。もう現実の夏よりだいぶ美しいですね。一年に5回は絶対聴きます。この曲に関してはこの記事で詳しく述べております。
「苦悩の人」 はっぴいえんどの「風をあつめて」をサンプリングした曲。
「冬へと走り出そう」 代表曲。打ち込みのドラムとギター、ベース、キーボードをフィーチャーしたちょっと他と毛色の違う曲。スタイル・カウンシル (Shout to the top) と佐野元春 (Happy Man)の曲の歌詞を引用しています。
82位 Going Steady『さくらの唄』2001年

銀杏BOYZの前身であるGoing Steady(通称ゴイステ)の代表作。安達哲のマンガからタイトルを拝借したセカンドかつラストアルバム。99位で紹介したハイスタの『MAKING THE ROAD』と並んで直撃世代の青春を彩った重要な一枚だと思います。1曲目から4曲目までの流れが特に素晴らしいです。全体的な勢いは銀杏の方が上ですが、ロマンティックさが際立つゴイステ、本作の方が筆者は好みです。
おすすめの曲
「アホンダラ行進曲」 銀杏まで行くとやっぱりやりすぎ感があるからこれぐらいが好き。アルバムのオープニングとして理想的な曲。だだっ広い一本道に風だけが吹いている感じが本当にする。ゴイステの勢いのある感じは好きなんですが、この曲のイントロのように静かでロマンチックな部分の方が実は個人的にはツボ。
「銀河鉄道の夜」 ハイスタに「STAY GOLD」があるように、ゴイステにもこの曲があるんです。童話的な詩世界と美しいメロディ、パンク的な勢いをマッチさせた名曲。間奏部分でバッハの『主よ、人の望みの喜びよ』がかなでられます。銀杏でもセルフカバーされていますね。
81位 リブロ『胎動』1998年

ラップの自己賛美(セルフボースティング)や攻撃的な所(ディス)が苦手、かといって明るくパーティっぽく騒ぐラップも嫌だっていう人も聴けるヒップホップアルバム。遣る瀬無い感情が言葉になっててスッとする1枚。このアルバムはディスクユニオンで流れてたのを偶然聴いて即購入したので筆者としても思い出深い一枚。
おすすめの曲
「胎動」タイトルトラック。ラップはやはり語り手、ラッパー自身を主人公として、一人称的に語りが展開していくことが多いのですが、この曲はちょっと違います。この曲を聴いているリスナーを代弁しているような、そんな内容。なのでラップ初心者でも共感しやすい内容ではないでしょうか。
「雨降りの月曜」これも基本的には「胎動」と同じで、ラッパー自身が主人公というよりは、憂鬱な雨の月曜の心持ちを代弁したような曲。
まとめ 90位から81位
以上、90位から81位まででした。
Hip Hop/ラップのアルバムがランクインしてきましたね。81位リブロの『胎動』、83位かせきさいだぁの1st、84位の『私を鬼ヶ島に連れてって』です。結構ラップアルバムが多くランクインしてくるランキングであることは予言しておきます。
80位から71位に続きます。