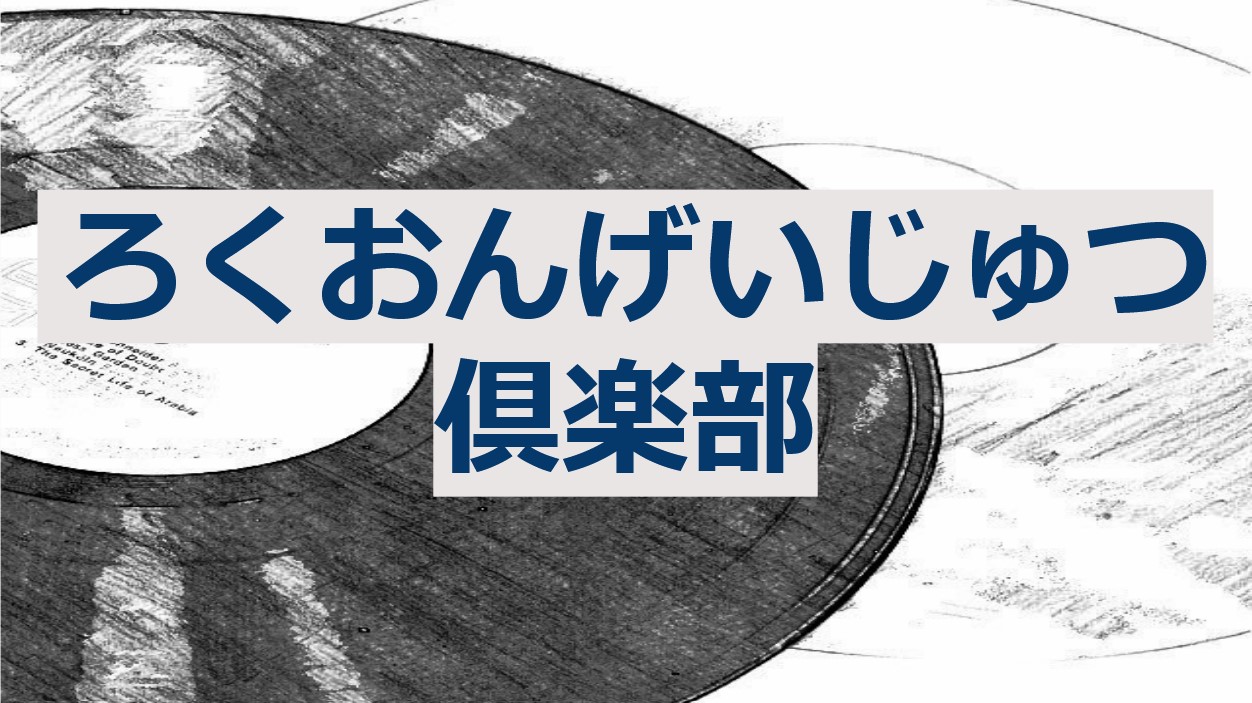今回はレディオヘッド (Radiohead) の「ザ・ナショナル・アンセム」(The National Anthem) という曲について解説、解釈します。
発表当時かなり物議をかもしたアルバム『キッドA』に納められている彼らの代表曲です。
かなり簡潔で分量の少ない歌詞ですが、どんなことが歌われているのでしょう?
また、その音楽性についても考察していきたいと思います。
1. 発表までの背景
レディオヘッドは現在でも第一線を走り続けている、イギリス出身の大物ロックバンド。
もうロックバンドという形容が正しいのかどうか疑問もありますが。
彼らは1992にデビューしましたが、瞬く間に90年代を代表するアーティストになりました。
デビューアルバム『パブロ・ハニー』Pablo Honey (1993) からはシングル「クリープ」(Creep)が大ヒットします。
続くセカンドアルバムの『ザ・ベンズ』 The Bends (1995)でギターロックの最高峰的作品を早くも作り上げまして、三枚目の『OKコンピューター』OK Computer (1997) で評価を決定的なものにして、90年代を代表するアーティストになりました。
「ザ・ナショナル・アンセム」は2000年に発売された『キッド A』(Kid A)というアルバムの3番目に入っている曲です。
『Kid A』は2000年代のベストアルバム選でもかなり上位にランク付けされる、いわゆる歴史的名盤と呼ばれるようなアルバムです。
音楽性を大胆に変化させて、シーンの様子まで一変させてしまったそんなアルバムです。
この『Kid A』に収録の、今回紹介する「ナショナル・アンセム」という曲は、彼らのキャリアにとって結構重要な曲だったりするんです。
というのもこの曲のSaturday Night Live(アメリカの有名な歌とコントのコメディ番組)での演奏が話題になり『Kid A』はアメリカでも売れに売れ、実験的な内容だったにも関わらずアルバムは全米一位を獲得してしまったんです。
では具体的に曲の解説に入ります。
2. 10年以上あたため続けたベースライン
まず音楽的なことからいきましょう。
実にかっこいいベースラインから始まりますね。
このベースラインはボーカルのトム・ヨーク (Thom Yorke) が16歳ぐらいの時に思いついたベースラインで、この録音でも彼が弾いています。
ずっとあたためたくなる気持ちはわかりますね。
この曲はほんとにこのベースライン思いついた時点で勝ちだなと言う感じです。
正規のベーシストである、コリン・グリーンウッドは、さぞ悔しがっていることだと思います。
それぐらいおいしいベースラインですね。
音楽的なところもうちょっと踏み込んでいきましょう。
3. シンプルながらも多様な音楽性
ベースラインとそれに絡むドラムを中心としたサウンドが続いていきます。
この曲には歌が入ってるんですけど、1分過ぎても歌が入ってこない。
これはもう考え方としてはもうダンスミュージックとかテクノ的な聴かせ方です。
最初にベースラインとそれにからのドラムのおいしいところずーっと聴かせているわけですね。
途中でドラムのシンバルがはいってきて、そのまま、また違う美味しいビートのコンビネーションをひたすら聴かせていきます。
そこにホーンセクションがからんでくる。
この美味しいリズムをずっとたのしんでくれっていう、構造的にはテクノに近く、ループという観点ではヒップホップに近い考えで進んでいきます。
そこにフリージャズ的なホーンがからんでいくのです。
4. タイトルが全体を定義する
それではやっと歌にはいったところで、歌詞を見ていきましょう。
この曲の歌詞を紐解くにあたって1番大事なのはこの曲のタイトルです。
この曲のタイトルはナショナルアンセム(The National Anthem)。
日本語に訳すと国歌です。
ではなぜタイトルが国歌なのか?
そんな疑問を念頭に置いて歌詞を見ていきましょう。
Everyone Everyone around here
Everyone is so near
It’s holding on
It’s holding on
まず最初のくだりですね。
直訳すると、これは、みんなが1カ所に集まって、みんなの距離がとても近いと言うことを指しています。
でポイントはですね。その近いと言う形容詞のnearに、soと言う強調の副詞が入ってる事ですね。
soはより感情的な強調表現になります。
ここの部分は、いろんな意味に取れますけど今ここで一番自然な解釈としては、都会のようなところをイメージしていてあそこに人が集まっている、そしてその距離がとても近すぎるというなことを言ってるんですね。
今一番至近な例でいくと、やっぱ東京での生活を思い浮かべてしまいます。
そのあとは
It’s holding on
というフレーズが繰り返されます。
Hold on というイディオムはいろいろ意味がありますので解釈は後回しにします。
複数の解釈が考えられる場合、なるべく、外堀から埋めていって選択肢を狭めていくのが、セオリーです。
ではこのitはなんでしょうか。
今までの歌詞の中で主語になりそうなものはeveryoneです。エブリワン自体は単数形として扱われますが、その代名詞としてうける場合はtheyなどが使われるのが一般的です。ということでこのitはeveryoneではなさそうです。
そうするとこのItって一体何なんだと言う話になります。そこで今一度タイトルに戻ります。
そうナショナルアンセムということで、国というのが主語になりえますね。
国や国家の代名詞としてはsheなどをつかなどを使うことも一般的にありますが、もちろんitも使用できます。
このitに関して言えば別に国家でなくても、例えばその人が集まっている都市であったり、会社であったり、システムであったりしてもいいと思います。
あえて特定しないことで解釈の幅が広がり、曲により包括的な意味合いを持たせることが可能です。
そこでHold Onと言うイディオムに戻りますと、一応ここには目的語はありませんから、素直に自動詞的な働きをすると取っておきましょう。
そこから考えてみるとHold Onと言うのは「持ちこたえる」という意味に取れるかと思います。
それの現在進行形、つまり国家やシステムが持ちこたえている、とここで歌ってるんですね。
みんなが集まって都市や国家を形成している。そしてお互いの距離が近すぎるという意味に取れます。
次のまとまりを見てみましょう。
Everyone Everyone is so near
Everyone has got the fear
It’s holding on
It’s holding on
It’s holding on
Everyone has got the fearと言うフレーズが初めてでてきますが、ここは素直に訳しますと、「皆その恐怖を抱いている」という意味ですね。
the fearがどういうものなのか具体的に明示されていません。
ここでは国家やシステム社会そういったものに身をおく中で、普段我々が感じている、恐怖、ストレスといったものを指していると考えて間違いないでしょう。
その後にまたIt’s holding onと言うフレーズが続いてきます。
つまり我々がそういった恐怖や不安を抱えた状態のまま、身を寄せあって非常にストレスフルな状況で暮らしている。
そんな我々を支えているシステムがなんとか持ちこたえた状態でいる、ということを繰り返し歌っています。
曲の後半に行くにつれて持ちこたえると言うフレーズがどんどん悲痛な叫びにかわっていきますね。
持ちこたえていると言ってるんですけども、これは逆に言うとですね、もう限界が近づいてきている、と言うことですよね。
つまりみんながストレスや不安を抱えていて、もう限界に近い状態であるということを歌っています。
それが混沌としたラスト付近のホーンセクションの演奏にも表れています。
5. 何故国歌なのか?
ナショナル・アンセムと言うタイトルに戻りましょう。
普通国歌というものは国やシステムを賛美したり、肯定するような曲調、歌詞、を有するわけですが、この場合はどうやら違いますね。
つまり今の我々置かれている状況にふさわしい国歌と言うものは、そういった正規の国歌ではなく、我々の状況を正しく表すのであれば、こういうものなんだということを、こういう不穏な曲こそが国歌にふさわしくなってしまっている、と言う皮肉、メッセージになっているんです。
まとめ
他にもいろいろな解釈が細かいところはできるかと思いますが、社会のこの混沌とした状況を音楽で表そうとする試みとである、と言う解釈は間違ってはいないと思います。
そういった状況などよく表れているレディオヘッドの代表曲の1つだと思います。
しかもそれぞれの音楽的な伝統を、彼らにしかできなえない方法でミックスして、非常にかっこいいサウンドをつくれているわけですね。
レディオヘッド曲の中でもの最高傑作の1つだと思います。
未聴の方はぜひ、聴いてみてください。