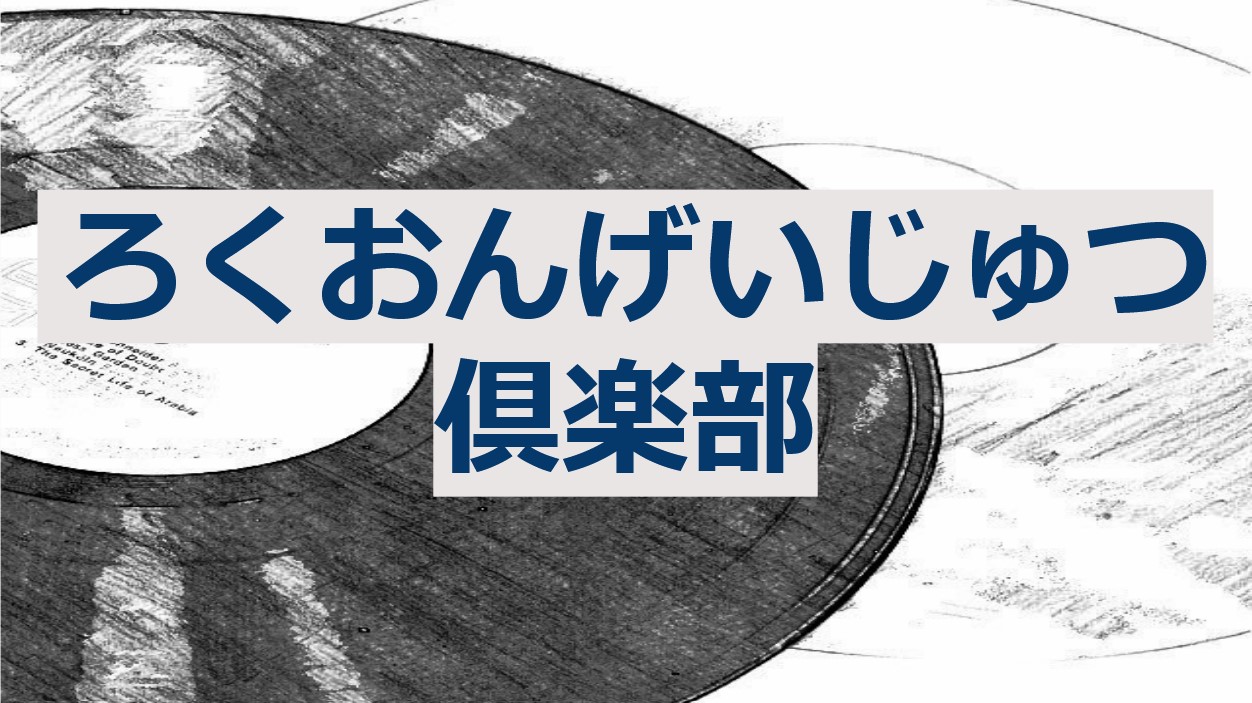この二か月の間に、スライ・ストーンが亡くなり、ブライアン・ウィルソンが亡くなり、オジー・オズボーンが亡くなり、そして渋谷陽一が亡くなった。そして我々の生活に直結する事として日本では参院選があった。それぞれの事象に対してどう思ったかを誠意をこめて書くとなると、それだけでこの記事が埋まってしまうので割愛させていただきたい。が、一言いうならば、亡くなったのは皆、現行の音楽シーンに今もってなお巨大な影響を与えてきたミュージシャンで、改めてその存在のデカさを思い知らされたという事だ。そしてみんな長生きできてよかったと思う。渋谷陽一も個人的にはこの四人の中で一番影響を受けたかもしれない。というわけで何かが大きく動いた様な心持ちにさせられる2ヶ月間だったわけだが、自分としては結構新しい気持ちで音楽に向き合えた様な気がした2ヶ月間だった。
『Daniel』Real Estate

去年(2024年)にでた、Real Estateの最新作。リリース直後もちょくちょく聴いていたが、やっぱり14年作の『Atlas』がいいやってなって、そっちばっかり聴いていた。ただ今はこの最新作を集中的に聴いていて、もう最新作の方が、少なくても今の気分にはしっくり来ている。前作『The Main Thing』が、悪く言えば自己模倣的な、過去の焼き直しの様なサウンドだったのに対して、今作はしっかりと今の音になっていた。具体的な変化として彼らのシグネチャーとも言えるボーカルのアレンジ、ユニゾンで複数の音源を重ね、音響効果が深くかかった浮世離れしたサウンドスケープ、がかなり控えめになって、ボーカルはハーモニー以外は基本重ねずに彼らにしてはナチュラルに聴かせている。各楽器の音響も今までの彼らよりも輪郭がはっきりとした音像になっており、そのクラリティに現代的なアップデートを感じた。例えば6曲目の「Freeze Brain」などはイントロからくっきりとしたドラムのビートが前面に出ており、それが心地よいのだが、この様な気持ちよさは今までに彼らのサウンドにはなかった。ただ、彼らのコアとも言えるメロディーのうっとりするような美しさや陶酔感は健在で、変化はあったが従来のファンを突き放すものではない。なので追っかけてない人にはパッと聴いただけでは以前からの違いがよくわからなくても無理もないかもしれない。
彼らの音楽は昔住んでいた町を放浪している自分を俯瞰で見るような白昼夢的サウンドといった趣だったのだが、今作は今住んでいる街をいい感じで歩いてるような、そんな心持になれるサウンドである。そんなちょっと地に足がついており、現実を見ながらもうっとりとできるサウンドが今の気分にフィットしたのかもしれない。4曲目の「Flowers」から7曲目までのながれが特に素晴らしく、そのあたりをかなり繰り返して聴いている。
大胆な冒険が見られるというわけでもないからか、どうも評論家受けはそれほどよくはない様だが充実作だと思うし、この先ずっと聴き続ける一枚だと思う。
「どON」LIP SLYME
リップスライムの活動からは諸事情で身を引いていたSUとPESが帰ってきてほぼ10年ぶりに5人が揃ったシングル曲で、今年(2025年)の4月にリリースされた。カムバックを祝う意味合いもあるだろうが、彼ららしいご機嫌なパーティーチューンに仕上がっており、まさに復活を印象づけるのにぴったりなナンバーだと思う。一番も二番もSUとPESをまず最初にフィーチャーし、二人の魅力が前面に出ている。SUの低音とPESの高音がもたらすコントラストは曲にメリハリとその高低差からくるローラーコースター的なダイナミクスを与えていて、これが彼らの大きな魅力の一つだったんだと今更ながら気づかされた。今回特に素晴らしかったのはSUで、歳をとった衰えなどは感じず、声にさらに渋みも深みが増してとても良く、他のメンバーとの掛け合い部分でも大活躍している。PESはDJ FUMIYAと並んで作曲にもクレジットされており、ラップ以外にも本曲に貢献しており、改めて、この五人じゃないとだめだなと思った。個人的には現時点で彼らの曲の中で一番好きで、これからの活動にまだまだ期待が持てる一曲。
『In Your Room』Airiel (2004)
シューゲイズというジャンルをかなり好んではいるのだが、いつも同じアーティストばかり聴いていてあんまり詳しくもない、というおかげでこんな出会いもある。Airielは最近初めて知った。彼らはイリノイ州シカゴ出身のバンドで、1997年ごろからずっと活動を続けている。この曲は連作で出した4枚のEPのうちの一つに入っている曲。ジャンルを掘るとなると、アルバム単位で紹介されがちだから、この様な形態でリリースされてしまうと紹介されにくいので、不利かもしれない。
硬質でややもすると打ち込みっぽい響きもあるドラムのビートが反復する長尺曲で、ディスインテグレーション期のキュアーがシューゲイズをやってみた様なサウンドで、その時期のキュアー同様ずっと聴いていられる。今回記事を書くためにあらためて見てみたらこの曲なんと9分以上あった。確かにイントロは長めだが、体感5分ぐらいなので驚いた。不思議とその発想はなかったが、アンビエント同様、良いシューゲイズは長ければ長いほど良いのではないかと思った。大げさではなく落ち着いた歌い方、声もいい。が、一応サビ部分に突入するときに徐々に音程が上がっていき、盛り上がっていく構造になっていてこれがまた効いている。歌詞の内容は、恋に恋する中学生が思い描いたような理想化された恋愛模様でこれもシューゲイズあるあるで、すべてがシューゲイズ/ドリームポップど真ん中で面白味がないと言われたらそれまでなのだが、そんなことはどうでもいいぐらいの没入感がある夢見心地な一曲。
『Time Out』the Dave Brubeck Quartet (1959)

説明するのが馬鹿馬鹿しいぐらい有名なジャズの名盤だが、このタイミングで好きになってしまったので仕方ない。リーダーは勿論デイヴ・ブルーベックだが、ポール・デスモンドのサックスの音色がとにかく心地よく、そちらにばかり耳がいってしまう。特にデスモンドが作曲した有名曲「Take Five」での音色なんか、音が滑らか過ぎて最初サックスだと思わなかった。『Time Out』というタイトルもそこから来ているのかもしれないが、今作の一つのテーマとしては変拍子がある。通常のジャズに使われる4/4拍子ではなく、5/4だったり、9/8(「Blue Rondo à la Turk」)だったり、6/4(「Everybody’s Jumpin’」「Pick Up Sticks」)だったりという楽曲が並んでいる。先の「Take Five」もそのタイトルが言っているように5/4拍子だ。が、テクニカルなロックグループが変拍子をあえて取り入れたときに陥りがちな罠、テクニックの押しつけには感じられず、あくまでも自然に聴かせ、変拍子にありがちなぎこちなさもない。とにかく「粋」で心地のいいアルバムになっている。もちろん曲の中でうまく4/4拍子に着地してある種の緊張を和らげてくれる場面があったりしてそこも上手い。というわけで非常に変なアルバムではあるのだが、Jazz入門としても最適だと思う。といっても、自分は何か書けるレベルまでピンとくるのに何十年もかかっているので、果たしてそういいきってしまっていいのかという疑問も残るが。
「Favourite」Fontaines D.C
広い荒野を見渡すように長い時間軸を見渡しているような曲だ。そこには今もあるし、過去もあるし、未来もある。聴いている間「僕たちは不死である」と感じさせてくれる。この感覚が簡単に共有できるとは、思ってもいないし「なにを大げさな」「度し難いセンチメンタリズム」と嗤うひとも多いと思う。でも、そういう感じ方ができることはとてもラッキーだと思っている。そして歌われているのは特別な、長きにわたる人間関係の話である。そこには二人の間にしかないきらめきのようなものがある。シンプルなコード進行に繰り返されるギターのフレーズ。ちりばめられる言葉の響きにはマジックが感じられてこの曲を特別なものにしてくれている。
彼らはどちらかというと不穏なものを作り出すのが得意だが、この曲のようにセンチメンタルなものも作り出せる。しかし、全盛期のリアム・ギャラガーを彷彿させる太々しさとのびやかな声の良さがありつつも、ぶっきらぼうにも聞こえるグリアン・チャッテンの歌い方もあって過度にセンチメンタルになっていない。過度にセンチメンタルにならない声というのはボブ・ディランにも当てはまるがこれは結構な利点で、長く飽きずにずっと聴けてしまうポイントでもあると思う。